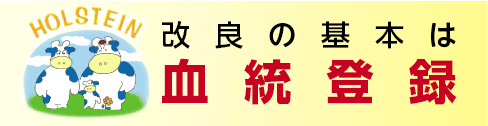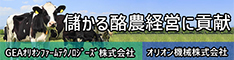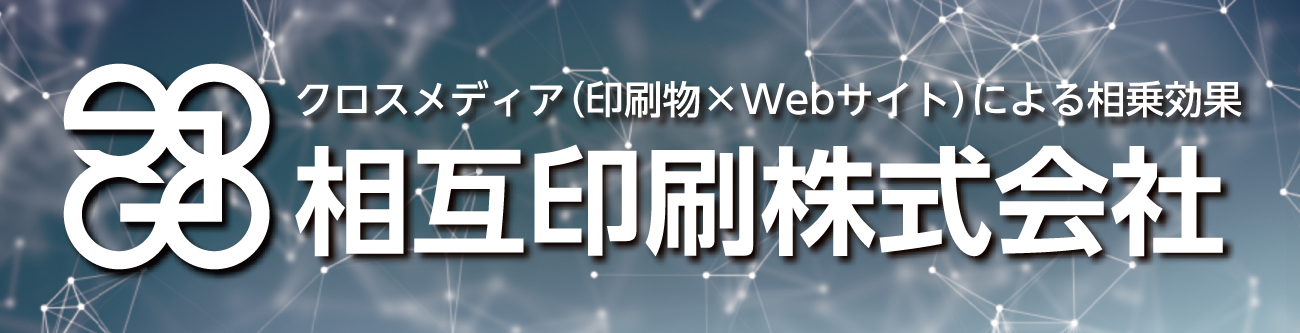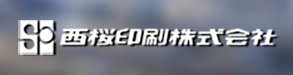全酪新報/2023年6月1日号
購読お申込みはこちらから
乳製品国貿 輸入枠数量据え置き バター、脱粉在庫は減少
農水省は5月26日、乳製品の国家貿易における輸入枠数量を検証した。バターはお土産や外食における需要が回復、脱脂粉乳は在庫低減対策の取り組み効果等によりいずれも在庫量は昨年より減少。現時点で必要量以上の在庫があることから23年度の輸入枠は1月に農水省が示した通り引き続きカレントアクセスの枠数量内(生乳換算13万7千㌧)に留め、品目別の輸入量は据え置く。-詳細は全酪新報にてご覧ください-
お断り=本記事は6月1日号をベースにしておりますが、日々情勢が急変しており、本ホームページでは、通常の態勢を変えて本紙記事にその後の情報も加えた形で状況を掲載するなど、一部記事の重複などが生じることもあります。ご了承ください。
環境整備推進会議 飼料価格変動 乳価反映へ議論 飼料版サーチャージ検討 渡邉局長が言及
農水省が5月26日に開いた「第2回畜産・酪農の適正な価格形成に向けた環境整備推進会議」の冒頭、農水省の渡邉洋一畜産局長は第1回会合で上がった意見を踏まえて、乳価へ生産コストを反映させる仕組み作りについて言及。「生乳取引において、配合飼料価格変動分を燃油サーチャージのような形で上乗せする仕組みの構築が実現可能かどうかなどについて、忌憚のない意見をお願いしたい」と呼びかけた。
4月下旬に開かれた第1回会合後に公表された議事概要によると、適正な価格形成に向けた仕組み作りと消費者への理解醸成について多くの意見が上がった。
このうち、適正な価格形成に向けた仕組みの構築については、「生産コストの中で大きな割合を占める飼料費について、燃油サーチャージ的な仕組みも検討すべき」「燃油サーチャージのような仕組みの検討に際しては、(買い控えを抑制するために消費者が)価格の上昇に納得できるよう、制度の見える化が必要だ」との意見が上がっていた。
このほか、コストを反映させる対象に飼料費以外を加えるべきとの声や、コスト反映のタイミングを即時とするか、半年から1年とするかなど、期間についても議論を必要とする意見などがあった。
消費者への理解醸成については、生産コスト高騰などで困窮する生産現場の声を感情に訴える形で消費者に届ける情報発信の方策の検討や、年齢層ごとに情報発信のやり方を区分けすべきとの声があった。
6月は牛乳月間 各地で活動

6月1日の「牛乳の日」を皮切りに、6月の「牛乳月間」の期間に合わせて、各地で牛乳・乳製品の消費拡大に向けた様々な取り組みが展開される。国内経済も徐々にコロナ禍の影響から回復している一方、飲用を中心とした家庭用需要は依然低迷。8月には飲用等向け乳価の引き上げ等に伴なう製品価格の改定が控える中、継続的な需要拡大、理解醸成に取り組んでいく必要がある。
牛乳月間には、農水省がJミルクと立ち上げた「牛乳でスマイルプロジェクト」のメンバーもそれぞれ取り組みを実施していく予定。また、活動に使用できるポスターも作成した。
このうち農水省は、酪農に関する展示イベント等を実施。このほか各団体・企業が牛乳等の無償提供や販売促進、プレゼント企画、レシピの発信、牛乳消費の呼びかけなどを通じ消費者へ呼びかける。
乳協・宮原会長 地道な対応策が価値向上に 業界の叡智を結集し課題解決
緩和している生乳需給や持続可能な酪農乳業の実現、国際化の進展への対応など山積する諸課題をめぐり、日本乳業協会の宮原道夫会長は「柔軟な心を持って、一つ一つ地道に対応策を積み上げていくことが酪農乳業界の価値向上に繋がると確信している。業界の叡智を結集して課題解決に務めていきたい」として、引き続き関係者の理解・協力を呼びかけた。乳協が5月19日に開いた総会後の懇親会の中で述べたもの。
乳業メーカーをはじめ、地域の牛乳協会や関連企業など多くの業界関係者が懇親会に出席した。そのうち来賓出席したJミルクの川村和夫会長は、昨年11月や今年8月の飲用向け乳価等の改定について触れ「酪農の厳しさについては我々もそこに寄り添う形でこれまで乳業として出来る最善の努力をしてきたと思っているが、今度は酪農現場の厳しさがある意味で乳業にバトンタッチされる状況ではないか」との認識を示した。
その上で「新しい価格体系の中で、牛乳・乳製品の価値をしっかり認めてもらうことにより、酪農乳業の危機も突破できるのではないか。取り組まなければならないことはまだ沢山残っている。関係者と連携してこの危機を突破していきたい」と強調した。
日本乳業協会 新会長に松田氏(㈱明治社長) 乳の価値向上など推進
5月19日に乳協が開いた定時社員総会では、任期満了に伴う役員改選も行われ、宮原道夫会長が退任。松田克也氏(㈱明治代表取締役社長)が新たな会長として就任した。総会後の懇親会の席上、松田新会長は「前任の宮原会長により進めていただいた改革や乳に関する価値向上など、しっかりとバトンを引き継いで進めていければ。乳を取り巻く環境は非常に厳しいものがあるが、品質や安全、サステナブルを常にしっかりと意識して、現状における足元の課題である需要拡大に向けて皆さんとともに取り組んでいきたい」と就任にあたっての抱負を述べた。
 「牧場で輝く家畜の命」連載㉕瀧見明花里さんの写真エッセイ
「牧場で輝く家畜の命」連載㉕瀧見明花里さんの写真エッセイ

井上牧場(北海道滝上町)の放牧地

仲良く草を喰む2頭のガンジー牛
6月。やっと暖かくなった北海道は、緑が綺麗な季節となりました。冬の間は牛舎で寒さを凌いでいた牛さんたちも、それぞれ放牧地で赴くままに過ごしています。
一方で私も、長い冬を乗り越えた後の撮影は格別。牛たちが青草を喰む音や、「モッチャモッチャ」という反芻音、鳥の鳴き声をBGMに、暑過ぎず寒過ぎない気候、青空、緑、牛たちという、絵のようなシチュエーションを前にして思わず「最高!」と声に出して喜びを噛み締めます。
そんな牧場タイムを過ごしていると、2頭のガンジー牛が仲良くしているところに遭遇しました。気付かれないように一歩、また一歩近づく度にシャッターを切り、もう少し近づけるかと右足を出した、その瞬間!牛さんに見つかってしまい、同時に「なに見てるのよ!」と言わんばかりの目線をいただきました。まるで、見てはいけないものを見てしまったかのようで、咄嗟に「失礼しました!」とその場を後にした私でした。(全酪新報では毎月1日号に掲載しています)
プロフィール
瀧見明花里(AKAPPLE)

農業に触れるためニュージーランドへ1年3ヶ月渡航。2017年より独立。『「いただきます」を世界共通語へ』をコンセプトに、牛、豚、鶏をはじめとする家畜動物を撮影、発表。家畜の命について考えるきっかけを届けている。
※写真の無断使用はご遠慮下さい