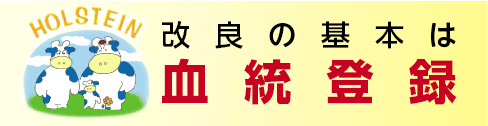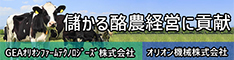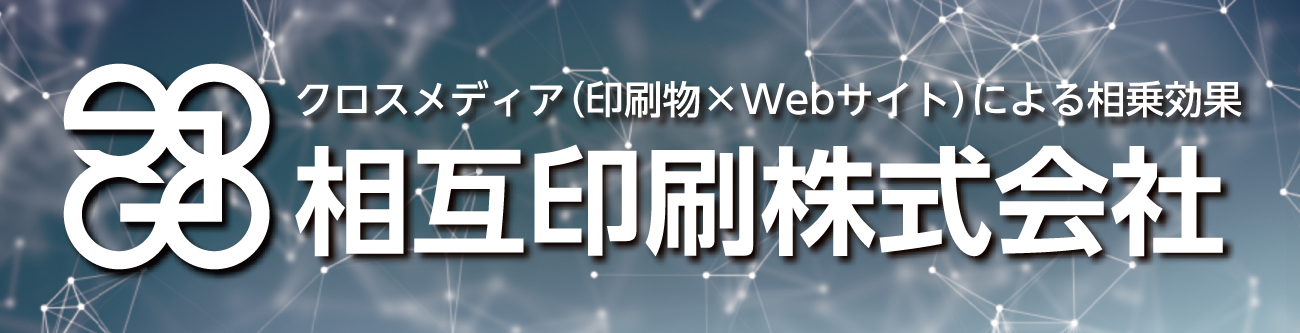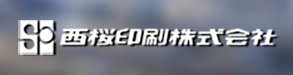乳滴/2021年9月1日号
酪農家戸数にも視点を

都府県では離農した酪農家の生乳生産量を継続している酪農家が規模拡大でカバーしきれず、生乳生産量が減少を続けてきた。ようやく0.1%増と微増ではあったが、昨年度、8年ぶりに前年度を上回った。
7月30日公表のJミルクの生産見通しによると、今年度も都府県は0.6%増と2年連続で前年度を若干上回る見通しだ。全国では1.7%増、北海道は、引き続き堅調で前年度を上回る2.6%増の予測となっている。
この背景には、減少に歯止めをかけるべく、国の事業や生産者団体等の取り組みによる近年の生産基盤対策が実ったことが挙げられる。ただ、悩ましいのは工業製品と違って生乳生産は、短期間で増産、減産といった調整が困難であることだ。そのため新型コロナ禍による現状の乳製品の過剰をどのように解消していくか、その対策には課題が山積している。
酪農家戸数は1963年の約42万戸をピークに60年近く継続して減少を続けてきた。最新(既報)の21年2月1日現在の畜産統計では、北海道が120戸減(2.1%減)、都府県が410戸減(4.8%減)。
経営継承については、親元就農、第三者への継承、新規参入等、様々な事例があるが、酪農情勢に関わらず着実に進めなければならない。