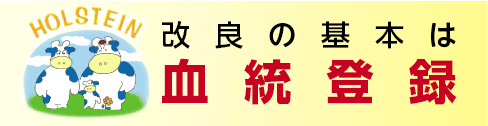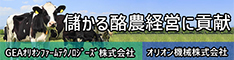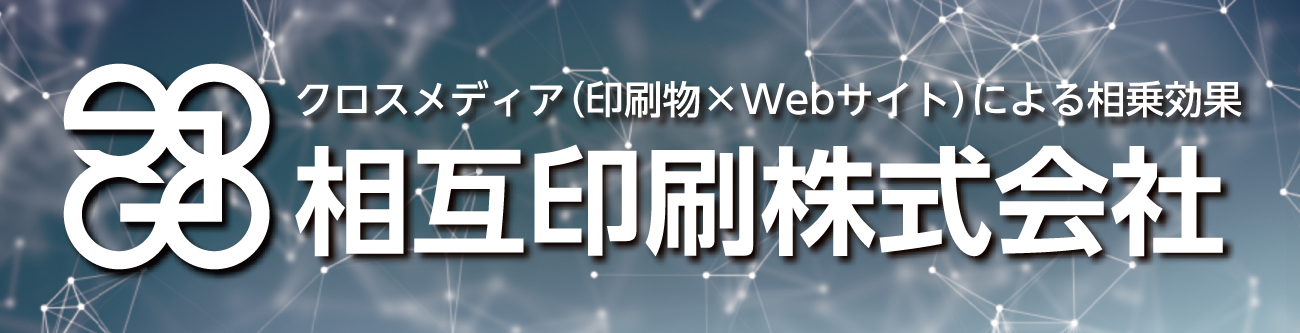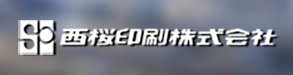乳滴/2022年6月10日号
美しい風景の裏側で

初夏の日射しに輝く牧草地。鏡の水面に揺れる早苗。各地でこの時期の日本ならではの風景が楽しめる。しかし豊かな田園風景の裏側で、農家の経済は火の車だ。配合飼料価格・燃料・肥料高騰。新型コロナ、ウクライナ侵略戦争、記録的な円安…。食料安全保障の観点からいえば国産資源の有効利用が重要であることは間違いないが、それは今いる農家がこの危機を乗り越えてからの話だ。
2006(平成18)年~08年にかけて米国でバイオエタノール需要が高まり原料トウモロコシ相場が高騰。そのあおりで配合飼料価格値上がりが続き、酪農経営を圧迫した。酪政連は酪農家のコスト上昇分の牛乳小売価格転嫁と生産者乳価の値上げを乳業に要請(07年8月)。中酪が「NO MILK, NO LIFE」のスローガンを掲げ都心で酪農理解醸成活動を実施(07年10月)したほか、各地で酪農家によるデモ行進などが行われた。
08年度、飲用乳価は2回(4月、09年3月)値上げされた。国も緊急対策として経産牛1頭当たり年間最大1万6500円を交付する都府県対策を決定。さらに加工原料乳生産者補給金の期中改定が初めてなされた(7月に30銭引上げ)。「今回の危機はあの時よりも深刻だ」というのが当時を知る方々の見解だ。対応は急を要する。