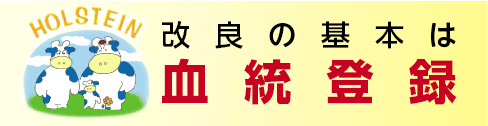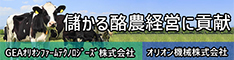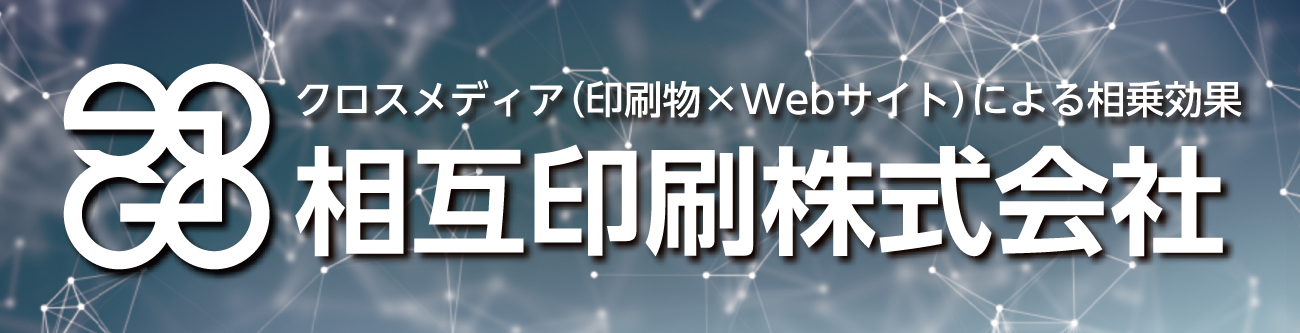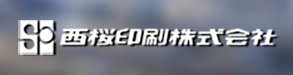乳滴/2022年12月1日号
生産抑制は苦渋の選択

11月以降の牛乳等値上げによる消費減少を加味しない段階で、単年度の生乳需給ギャップは約40万㌧程度はあると推計されていた。この膨大な需給の改善・適正化に向けて、いわゆる出口対策(乳製品在庫低減対策)が進められてきた。
これに加えて入口対策(生産抑制)も行われてきたが、国も今回の第2次補正予算案で支援し拡充されることとなった。やむを得ない情勢にあるが、酪農家にとっては、生産抑制は苦渋の選択、厳しく辛いものがある。
事業計画では24年3月までに約4万頭の乳用経産牛を早期リタイヤ(淘汰)。参加希望者は23年度に減少した乳量の水準は24年度も維持するのが条件とされ、生産抑制につながる。
生産量と関係の深い乳牛頭数の推移(前年比)を農水省・畜産統計から見ると、17年に2万2千頭減少し、132万3千頭まで減少。その後、増加に転じた。この5年間に4万8千頭、3.2%飼養頭数が増加している。
生産基盤の弱体化に歯止めをかけ、酪肉近で目標とされた30年度、780万㌧に向け進んでいたところに、新型コロナ禍とウクライナ情勢という想定外の事態が襲った。酪農乳業界にも大打撃となった。生産抑制の痛みを少しでも小さくするため需要拡大の底上げを頑張るしかない。