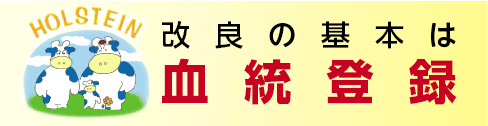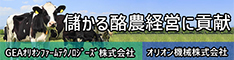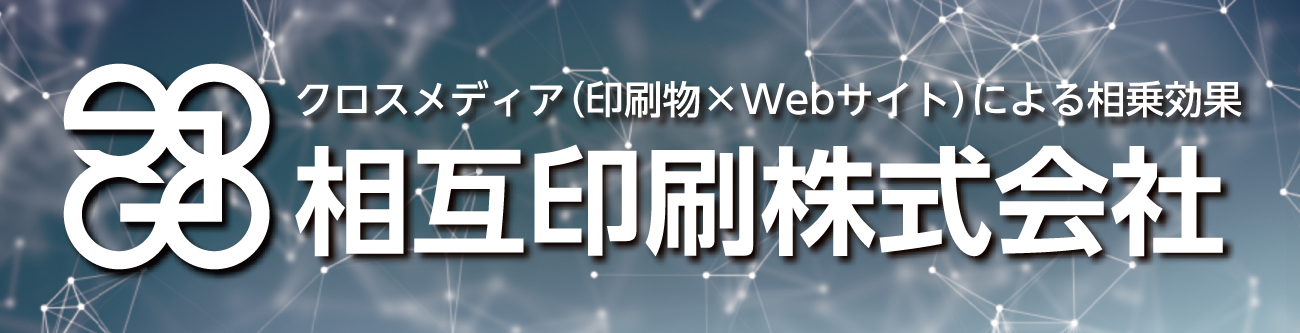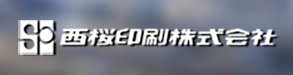乳滴/2023年2月1日号
酪農は1000日産業

「酪農は1000日産業だからな」と入会当時、北海道地区の役員に言われた。当時も生乳の生産調整で酪農界が大揺れの時代であった。簡単に生産を減らしたり増やしたりは、できないということだ。
誕生した乳牛(雌)が哺育・育成期を経て、生後約2年半で初めて出産を迎え、生乳を搾れるようになる。その後、毎日300~330日搾乳する。出産から約40日に次の人工授精を行う。この自然の営みは変わらない。
必要な時に必要な分だけ(部品を)供給してくれれば良いという工業の論理は、あまりに傲慢である。その究極のいわゆる「カンバン方式」は、近年、半導体不足で供給が遅れ、生産が停滞した自動車産業を見れば、一部は見直さざるを得なくなりつつある。
新型コロナ禍や人手不足による物流の混乱、ロシアのウクライナ侵攻による地政学的リスクや資材の高騰。理論上では、最も生産効率を高めるはずであったものが、工業の世界ですらほころび始めた。
「(酪農を)やりたいというなら、やらせるが、息子に継げと言える状況にはない。ただ、必ず状況が良くなると信じて今は頑張っている」と堅実経営の酪農家ですらこの状況だ。酪農家がいてこそ生乳の安定供給ができる。