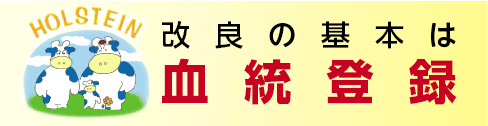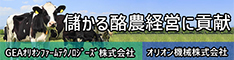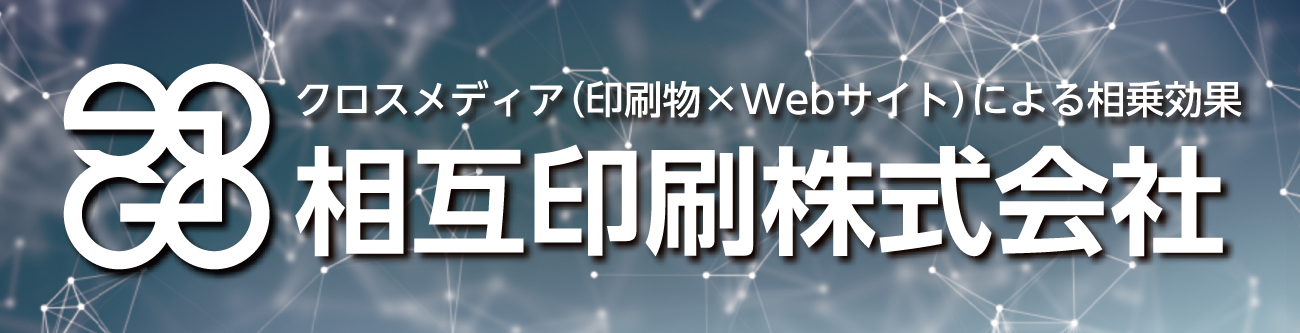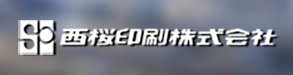乳滴/2018年9月1日号
「胃の痛くなる季節に」

夏休みが終わり生乳需給は、学校給食牛乳(学乳)が再開される9月の最需要期に入った。牛乳消費に占める学乳の割合は12%(2016年度、生乳生産量全体では5.2%)。子供たちには最優先で供給しなければならない。
7月から記録的な猛暑や西日本豪雨、相次ぐ台風等の災害により、都府県の生産現場では一段と乳量が落ち込んでいる。乳業者側では、量販店等に特売の自粛や一部では新規の注文を減らしたり出荷調整を行う等の対応を実施し備えてきた。
もともと、生乳生産は暑さで乳牛の体力が落ちる夏場は減少し、冬場には増加する。一方、需要は夏場に増加し、冬場に減少するため、必然的に季節的(構造的)な生乳の需給ギャップが生じる。その調整弁となってきたのが、乳製品の製造であり、北海道や九州からの生乳の移出である。
ちなみに17年の北海道からの生乳移出量は約43万9千㌧。これに飲用牛乳(産地パック)の移出量約39万4千㌧を加えると合計83万2千㌧、前年比8.4%増だった。
ただし、この移出量の拡大にも限界は出てくるだろう。人手不足の中での輸送の運転手の確保、輸送タンク等の設備の問題もある。台風によるほくれん丸欠航もある。需給調整や流通関係者には胃の痛くなりそうな季節である。