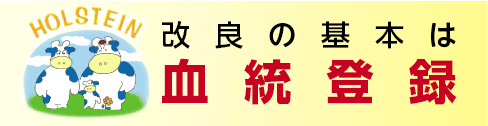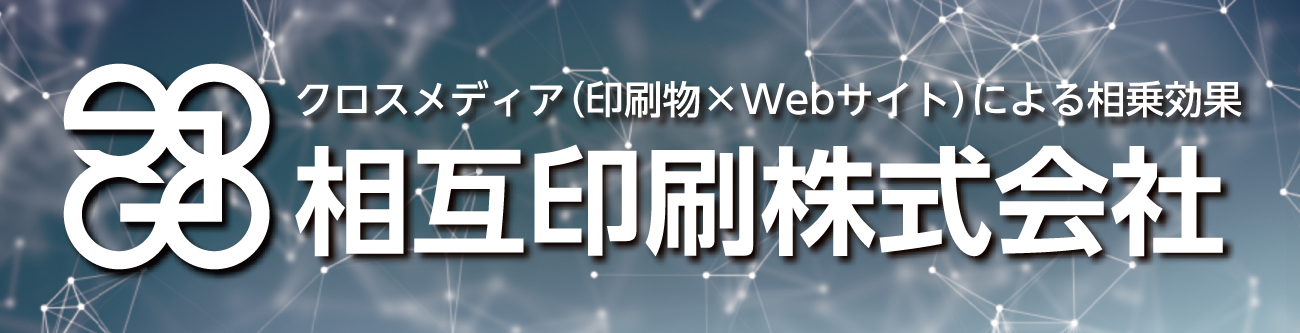酪農と文学 連載16
文豪がチーズ小屋の情景や牛舎を描写するとどんな具合に表現するのでしょうか。こうした素材をきめ細やかに作品にもりこんだものはあまり見当りませんが、今回はアンドレ・ジードの作品「地の糧(かて)」を紹介します。
ジード自身が牧場を所有していたといわれていますから、チーズ作りや、乳牛がいる牛舎内部の表現はお手のものかと思うわけですが、この作品は小説ではなく、散文詩ですから、少々理解しにくい点もありますが、読む人次第で、美しい文章だと思う人もいれば、あれだけの文豪が、こと酪農業に関すればこの程度の表現か、とまちまちかと思います。
地の糧―アンドレ・ジード 著アマゾンで検索
文豪が描写したチーズ作りや牛
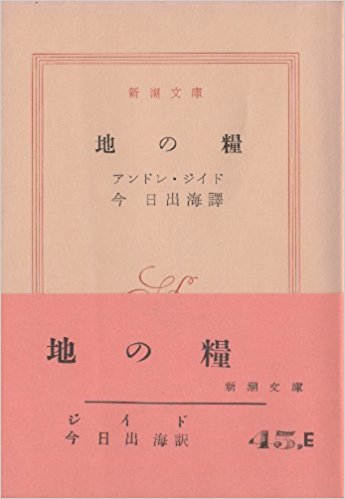
作者についてこまごまと紹介するわけにはいきませんかが次に取りあげたチーズ作りの、というよりチーズ小屋にかかわる個所と、牛舎の中での追憶らしきものを交えた文書をお読みいただく前にこれだけ知っていただければと思います。
ジードは幼年時代は現代風にいうと〝落ちこぼれ〟少年であり、しかし厳格な母のもとでかなり宗教的な枠の中で育てられたこと。心機一転、猛勉強し、小説家を志したこと。男色家であったこと、従って結婚した妻とは性交渉が無かったこと。共産主義への共鳴とその後の離反など―そして牧場を経営していたこと。
さて、この「地の糧」は多くの章に分けられており、その中に農園の章があります。これから紹介する文章はその農園の中の一部です。この散文詩は穀物倉庫をスタートし農家の物置とつづき、三番目に出てくるのが搾乳場(チーズを作る部屋)の描写が次のようにでてきます。
『第三の扉は搾乳場の扉だ。休息。沈黙。チーズが圧縮されるあのふるいのひっきりなしの排水。金属管の内でバターのかたまりが圧搾される。七月のひどく暑い日には、凝乳の匂いはいっそう清冷で、いっそう味気ないものに思われた……いや、味がないのではない。鼻孔の奥でしか感じられないほどかすかで、薄色の辛味を帯びていて、すでに匂いというよりはむしろ味なのだ。この上なく清潔に保たれている攪乳器。キャベツの葉に添えたバターつきプチ・パン。農婦の赤い手。常にあけ放されているが、猫やハエが入り込まぬように金網が張った窓。クリームが表面に浮び上がるまで、いつもいっそう黄色い牛乳を満たした鉢がたくさん並んでいる。クリームはおもむろに平らになる。それから膨れ、しわができ、乳しょうの皮がはげる。乳しょうが全くなくなると、持ち去られる……(しかしナタエル、君にすっかり話すことは不可能だ。私には百姓をしている友人があるが、彼はこうしたことを見事に話す。彼はどんなものでも効用があるものだと説明する。そして、乳しょうもどんなに捨てたものでないかを教えてくれる)(ノルマンディではそれを豚に与えているが、どうやらもっとよい用途がありそうに思えるのだ)』
チーズ作りが臭覚によってとらえられたり、乳しょうを豚のエサでなく、何かに利用できないものかなど詩人と経営者が入りまじって興味深い文章です。
さて、第四の扉は牛舎の内部へと開かれていきます。
『第四の扉は牛小屋に向かってひらいている。牛小屋はたまらない蒸し暑さだが、牝牛はいい匂いをしている。ああ!……汗ばんだ肌がいい匂いを立てているあの農夫の子供たちとともに、牝牛の脚の間を駆けまわった時代に、私がいるのならば。我々はまぐさだなのすみに卵を探したものだ。また、数時間、牝牛の群れを眺めてもいた。牛の糞が落ちて、はね返るのを眺めていた。どの牝牛がいちばん先に糞をするかかけをした。そしてある日、私は突然そのうちの一匹が犢(こうし)を産み落すのだと思うとこわくなって、逃げだした。』
牝牛はいい匂いがする、とか乳牛の糞が飛び散る情景など現実に牧場経営をしていたジードでなければできない表現かと思います。若し読者のみなさんが、わが家の牛舎の内部を詩的に文章にするとすれば、どんな表現をしますでしょうか。
本連載は1983年9月1日~1988年5月1日までに終了したものを平出君雄氏(故人)の家族の許可を得て掲載しております。