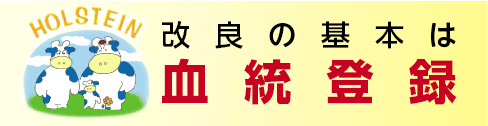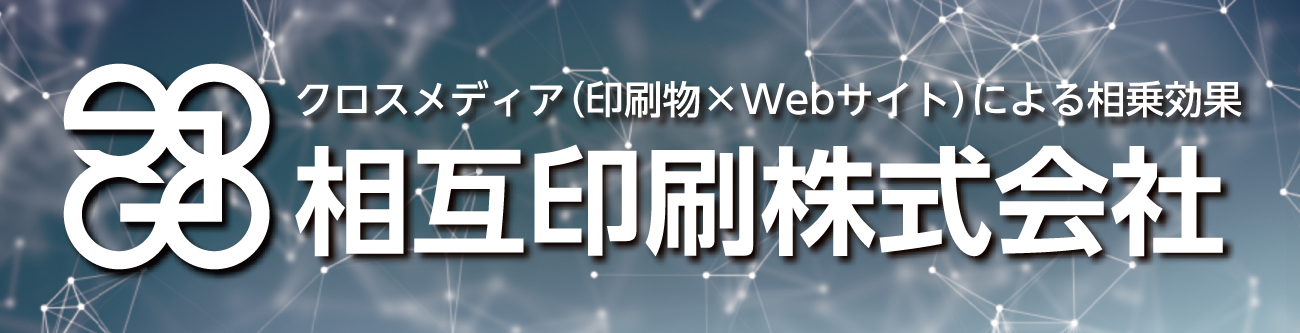酪農と文学 連載9
レジスタンス作家、フランスのヴェルコールの「海の沈黙」を今回はとりあげます。この作品はドイツ占領下でドイツの監視の目をのがれながら出版された秘密出版されたものですがこのため皮肉にも短編小説の地位が守られた結果となるのですが、そのことはともかく、牛乳を文学作品の中で読者に多くの考えをはりめぐらすラストシーンに登場させていることに驚きを感じます。日本も国民が200cc位毎朝飲むようになればわが国の短編小説にも牛乳が登場してくるのでしょうか。
海の沈黙―ヴェルコール 著アマゾンで検索
朝は黙って牛乳 日常の奥に哀歓
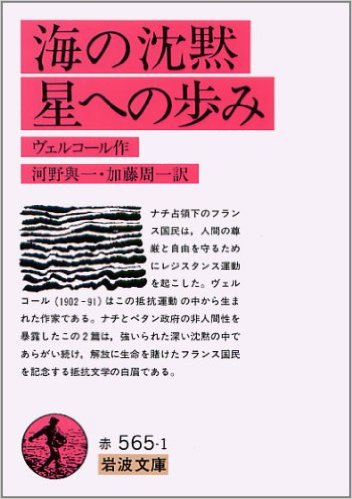
古今東西、たくさんの文学作品はあるが、小説の巻末をしめくくる文章が牛乳を飲む描写で終っている小説はまれでしょう。短編小説であるからこそ、この日常のさりげない働きを読者に投げ出して、後は読者の無限の思考にまかせてしまう。
この無名の版画家であったヴェルコールの「海の沈黙」という短編小説のスジはドイツ占領下のフランスの田舎町に年老いた作家とその姪とが住んでいるが、そこにフランスびいきの背の高いびっこのドイツ将校が寄宿し、二人との交流を描く、ドイツ将校と老作家の歩みよりは感じられ(自国の文学や音楽をとおして)ても、ドイツ将校と姪とは長いながい沈黙しか描かれていません。
姪の沈黙はフランスの沈黙であり、老作家の歩みよりはフランスの歩みよりなのでしょうが占領軍(ナチス)将校と占領下にあるフランス人との壁は厚く破ることができない。
しかし、このびっこのドイツ将校は懸命にこの壁を破ろうとします。そしてパリーに出向いて行った時、そのことを同国人に向って試みますが勝ちほこる同僚の前では一笑にふされてしまうのです。彼のもつフランスへの理解と同調が強ければ強いほど結果はみじめになる。
彼は決意し、最前線の部隊への配属を志願し、老作家と姪の住む田舎にもどります。
死を決めたこのドイツの将校が夜、二人の前に姿をあらわすが、苦しみと悲しみにみちた表情などを次のように描写しています。
『(前略)とつぜん、顔じゅうの皮膚が地下の振動をつたえるように、ぶるっとした―湖の面に微風がさっと吹きわたったようだった。わかしている牛乳の表面に泡がたちはじめるときの、クリームの膜のようだった。その眼は、姪のみひらかれた生気のない眼をしっかりとらえた。(中略)自分を責めさいなむようにくりかえした「望みはないのです。望みはないのです。」(後略)』
この後、彼は東部戦線の屍体となる決意でいいます「地獄行きです」と。
この小説では、登場する老作家の姪はこのドイツ将校と一言も口を開きませんが最後に「おやすみなさい」といって部屋をでようとするこの男に一言応えます「ごきげんよう」。この最初にして最後の一言はこの小説の中でいろいろの響きと意味をもつのではないでしょうか。
いろいろ筋書きをいってみても理解しにくいと思いますが、作者ヴァルコールはこの小説を虐殺された詩人(実在の人物)サン=ポリ=ルーの思い出に書いている事実です。この詩人と娘は実際ドイツ兵に襲われ、娘は強姦未遂で入院、女中は惨殺されそして、その病院で老詩人は沈黙のうちに死ぬという悲劇的な現実を背景に作者は筆をとっているわけです。
しかし、この作品には暴力、強姦、惨殺、掠奪など何もでてきません。そうです姪の〝沈黙〟です。この沈黙が作品の中で浮きぼりにされますが最後に「ごきげんよう」の一言は一体何を表現しているのでしょうか。
背の高いびっこでハンサムなフランスびいきのドイツ将校が地獄へ旅立った後朝のひとときを最後にこの短編小説は終っています。まったく、いつも迎える朝の平凡な描写です。ここに牛乳が登場します。
『あくる日、朝の牛乳を飲みにおりてきたとき、かれはもう発ったあとだった。姪はいつものとおり朝食の用意をすませていた。黙って給仕してくれた。2人とも黙ったまま飲みおわった。そとでは靄ごしに、光りのうすい太陽が照っていた。とても寒いという気がした(1941年10月)』
このモヤのかかった寒そうな10月の朝、老作家とその姪はあたたかい牛乳を飲んだのだろうか、それともつめたい牛乳だったのだろうか。
本連載は1983年9月1日~1988年5月1日までに終了したものを平出君雄氏(故人)の家族の許可を得て掲載しております。