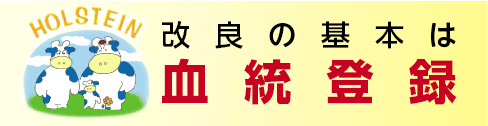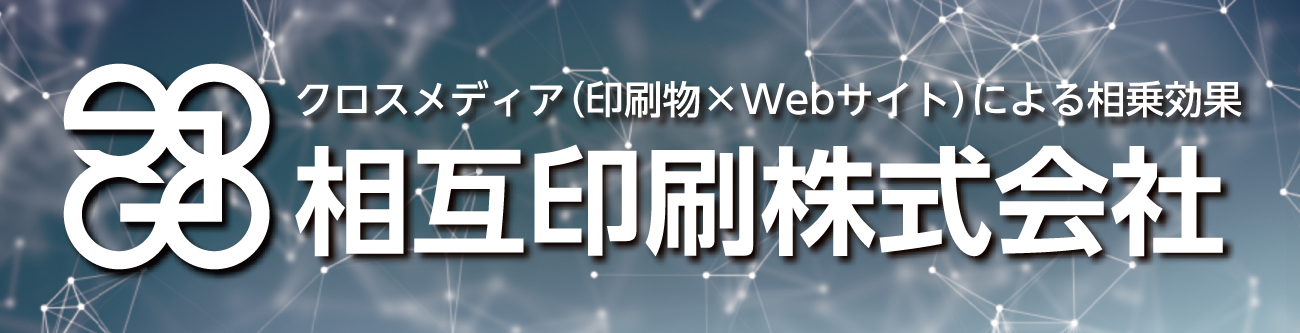酪農と文学 連載6
今回はアーネストヘミングウェイの〝武器よさらば〟からチーズとのかかわりあいを取り上げました。この第1次世界大戦のイタリア戦線を背景とした恋物語りにはチーズが何回もでてきます。
最前線の塹壕の中、恋人と一緒の時の街中のショーウインドの中のチーズの山、レストランでのサンドイッチの中のチーズ等、しかしなんといっても砲撃中に主人公に抱きかかえられて駆けるチーズの描写です。
ヘミングウェイの小説中、これほどチーズが小説中の小道具として印象に残るものは他に見あたりません。
武器よさらば―ヘミングウェイ 著アマゾンで検索
砲弾炸裂 戦線を駆けるチーズ
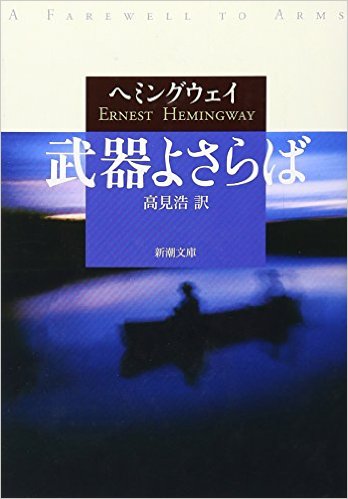
チーズが戦場においてこれほど駆けめぐった小説はまれでしょう。この小説は戦争を舞台とした恋愛小説として位置づけられると思いますし、事実、第1次大戦のイタリア戦線において、イギリスの篤志看護婦のキャッサリンとアメリカの義勇兵フレデリック・ヘンリーとの恋と死との物語りとなっています。
この小説の最初の節目となる二人の出会いそして前線に出た主人公フレデリック・ヘンリーの負傷という設定がありますが、主人公の重傷の直前に登場するのがチーズです。
最前線の塹豪で戦況や自分達がおかれた状況、戦争へのちょっぴりした批判めいた会話のあと主人公は部下の1人をともなって食事を受けとりに出向く、マカロニ料理だけの配給に主人公の申し入れでチーズも手に入れ塹豪にもどるわけですが、その途中にものすごい砲撃に出くわすわけです。
チーズをしぶしぶわけてもらう場面、そしてチーズが主人公の手の中に保護されながら駆けめぐる状況は次の文書を読んでいただければ十分でしょう。
『少佐が看護兵に言いつけると、看護兵は奥に入ってゆき、金属の鉢に冷えたマカロニ料理をもってきた。ぼくはそれをゴールディーニに渡した。「チーズはありますか?」少佐はいやいやながら看護兵に言いつけると、看護兵はまた穴にもぐりこんでいき、四半分にした白いチーズをもって出てきた。(中略)二人とも伏せた。炸裂の閃光と爆風と硝煙のにおいと同時に、破片のひゅっと鳴る音や、煉瓦ががらがらと落ちてくるのが聞こえた。ゴールディーニは立ちあがって、塹豪のほうに駆けだした。ぼくもチーズを持ったままそのあとを追った。チーズの滑らかな表面は煉瓦の埃でおおわれていた』
塹豪に逃げこんだ後、くさったような葡萄酒で、マカロニとチーズをノドに流し込む描写が次のように出てきます。そしてこの描写の後、敵軍の大砲撃がはじまるのです。戦士たちのノドをチーズが通過したかどうか……。
『みんなは鉢のまうえに顎をつきだし、頭をうしろに傾け、マカロニを端からすすりこみ、たべた。ぼくはもうひとくち食べ、チーズを食べ、葡萄酒を流しこんだ。外で何かがおちて、大地を揺り動かした。「42サンチ砲か追撃砲だ」とガヴーツィが言った。(中略)ぼくはチーズの残りを食べ、葡萄酒を飲みこんだ。』
このあと主人公は砲撃により重傷を負うが、部下が「おかあさん、ああ、おかあさん」と血の絶叫をあげて死んでいく描写などが続くわけですが、戦場という極限状況の中でのチーズを中心にした食事と、その最中の大混乱と恐ろしい程の実戦状況が、きわめて乾いたタッチで描かれており思わず息をのむほどです。
第1次大戦のヨーロッパですから、パンとチーズと葡萄酒は当然基本食糧でしょうが、チーズの塊がホコリをかぶって駆けぬけ、人間の胃に満足を与える間もなく飛び散る。いずれにしてもこれほど極限に追い込まれたチーズもめずらしい。
さて、前述したように〝乾いたタッチ〟と表現しましたが、作者へミングウェイはご承知のようにハードボイルドタッチの元祖のようなもので、その表現はムダがなくドロドロしたりネバネバした表現をはぶいています。それはチーズでいえば超硬質チーズを思わせます。その証拠に作者の作品にしばしば登場するチーズはただ「チーズ」とだけ表現されています。
この作品に書かれた、イタリア戦線における白いチーズで二キロ半ばかりの塊はいったい何チーズだったのでしょうか。ものすごい匂いをもつ軟質のリンバーガーチーズ(ベルギー原産)でないことは確かなのですが―。
この作品の中でチーズという言葉、表現は何ヵ所かにありますが、恋人キャッサリンに会うために脱走し、早朝のミラノ駅の酒場でコーヒーを飲むところが出てきますが、コーヒーに入れた牛乳の乳脂をとりのぞく描写が次のように出てきます。
『(前略)兵隊が2人テーブルにすわっていた。ぼくはカウンターの前に立って、コーヒーを1杯のみ、パンをひと切れ食べた。コーヒーはミルクがはいっていて白茶けていた。ぼくはパンの切れで表面のミルクの薄皮をすくいとった。主人はぼくをみた。(後略)』
さて、小説の大筋は最前線、大退却、混乱、同士討ち、脱走などとなるわけで、大半が戦場を舞台とするものだけに、パン、チーズ、葡萄酒の戦時食のオンパレードとなる。単調な食事の連続ほど人間をいらつかせるものはない。
しかし作者は主人公フレデリック・ヘンリーにその単調さのみを与えない。時には間げきをぬって美味しいものへの志向をほのめかす。
主人公がマティーニを再注文しながら、次のようにいわせている。
『(前略)サンドウィチが来て、ぼくはそれを3きれ食べ、マティーニをもう2杯飲んだ。ぼくはそんなに純食なのを味わったことはなかった。ぼくは赤葡萄酒や、パンや、チーズや、グラッパ入りのまずいコーヒーなどやりすぎていたのだ。』と。
しかし、パンやチーズにあきた主人公も、砲撃中の陣地をチーズの塊を必死にかかえてつっ走る主人公も同じフレデリック・ヘンリーなのだ。主人公とチーズはこの小説の中で見事にからみ合って熟成している。作家ヘミングウェイの確かな食文化のとらえ方を感じるのだが―。
本連載は1983年9月1日~1988年5月1日までに終了したものを平出君雄氏(故人)の家族の許可を得て掲載しております。