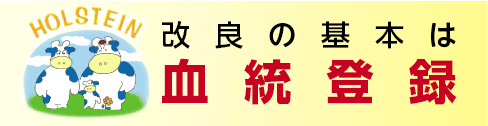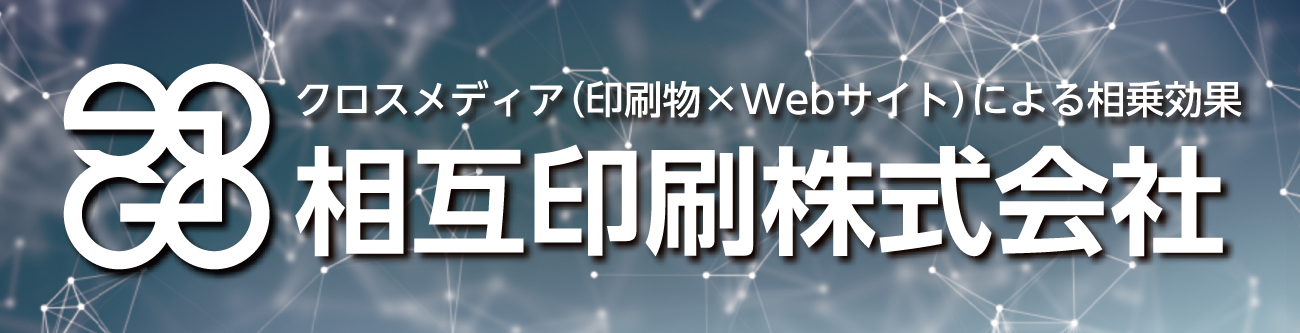酪農と文学 連載17
西欧には肉を食べない、牛乳を飲んだりしてはいけない日がある。しかし、それを本当に守っているのでしょうか。ほんとうに貧しければ多分「神よゆるしたまえ!」とつぶやきながら口に入れるでしょう。たとえば地獄行きでも。それが貧しさであり人間のしたたかさだ。――こと食べものに関しては作者チェーホフはそういっているような気がします。とてつもなく貧しさを感じるロシヤの農村と農民の中に登場する牛乳(多分この農家に飼養されている乳牛は自家飲用のための1~2頭)、老婆とその孫娘の間に、飲んではいけない日に登場する牛乳を紹介します。
百姓 チェーホフ 著
貧しい農村老婆 地獄行きでも牛乳
チェーホフの数ある作品の中で農民を描いた作品はたくさんはありませんが、この作品は豚にも劣る農民の生活を悲劇的に描いております。
モスクワのボーイとして働いていたニコライという男が料理を運んでいるとき転倒し、やむなく職を離れ、その治療にすっかり金を使い果たし、妻と1人娘(サーシャ)をつれてやむなく故郷に帰ります。
ところが、年老いた両親、長兄と妹夫婦、そしてその子供達を入れて12人の大家族に3人が加わりますから、足のふみ場もない程です。食べ物にも事欠く上に、寝る所さえわらをふとんに納屋暮しといった具合です。
長兄は幼児を含めた6人の子供がいながら酒びたりで、事あるごとに妻(マーリヤ)をなぐり、要するにたちの悪い酒乱の男です。
母親(ニコライの母)はいつもがみがみと孫達をしかりとばす。孫娘達がキャベツ畑の番をせず、がちょうが植えたばかりの苗をみんなつついて喰べたといって、棒で声も出ない程幼い孫娘2人をなぐりつけたりで、いつもこの農家には、うめきや、餓えや、悪臭や、どなり声が満ちているのです。
作品の中では放火のことや厳しい税金のこと、宗教的なことなどいろいろと農村や農民の姿を描写していますが、ここではそれにふれず、婆さん(ニコライの母)とその孫娘達の間に登場する牛乳を紹介します。
植えたばかりのキャベツの苗畑の番をしなかったためにがちょうに苗を喰べられたことに怒った婆さんは2人の孫娘をこっぴどくおしおきします。これが伏線です。さて、サーシャとモーチカの孫娘らは、このため婆さんが鬼ばばあに思えます。その悲しいにくしみを何かで報復しようと思うわけです。
今は、肉食をしたり酒を飲んだり、勿論牛乳を飲むこともいけない聖母昇天祭の精進期なのです。
牛乳を武器に2人の孫娘は画策します。
『マーリヤ(のんだくれの長兄の妻)は牝牛の乳を搾り、搾乳おけを持ってきて、それを腰掛の上へ置いた。婆さまはやがてそれを、同様長いことかかって、ゆっくり、ゆっくりとおけからツボヘ移した。今は聖母昇天際の精進期で、だれも牛乳を飲もうとはしないから、それがそっくり残るであろうことに、1人でほくそえみながら、そしてほんのちょっぴりフョークラ(末娘)の赤ん坊のために小皿へそそいだ。』
だれも飲まない、いや飲んではいけないので、いつもより牛乳はたっぷりある。婆さんは1人占めをもくろむ。だけど婆さんも人間だ。幼い孫のため(赤ん坊)には少々皿に牛乳をそそぐ。
ところが、これをみていたサーシャとモーチカは婆さん1人だけを罪深い人に追いこむ。地獄行きだ、とばかり次のように―――。
『それから彼女とマーリヤとがツボを穴倉に運んで行くと、モーチカは急にはね起きてだんろから這いおり、パンクズの入った木わんののっていたベンチのそばへ行って、木わん中へ皿の牛乳をあけてしまった。』
これで、婆さんだけが牛乳を飲んだから地獄おちだ『婆さまは小屋へ戻って行くと再び自分のパンクズにとりかかった。サーシャとモーチカはだんろの上に坐って彼女を見ていた。2人には婆さまが精進を破ったから今ではもう地獄に行くにちがいないことが嬉しかったのである。彼女達はそれになぐさめられて睡るべく身をよこたえた。サーシャは、うとうとしながら最後の審判の事を想像していた――陶器焼きのカマドのような大きなカマドがさかんに燃えていて、牛のような角のはえた全身まっ黒な鬼が長い棒で婆さまを火の中へ追いたてていた。ちょうど先刻婆さま自身がガチョウを追っていた時と同じように。』
牛乳が文学作品の中でこのような素材として登場するのはめずらしい。結局、ニコライは病死し、その妻と娘サーシャは夫の故郷に別れをつげ、女中でもしながら再び都会モスクワで暮らそうと去っていく。
暗く悲しい短編小説ですがサーシャの言葉や将来に作者は光りをあてて、農民像をやさしくつつんでいます。でなければ、ここに登場した牛乳も救われません。
本連載は1983年9月1日~1988年5月1日までに終了したものを平出君雄氏(故人)の家族の許可を得て掲載しております。