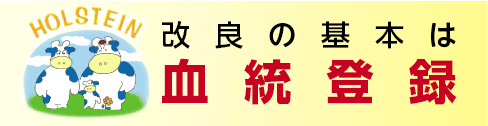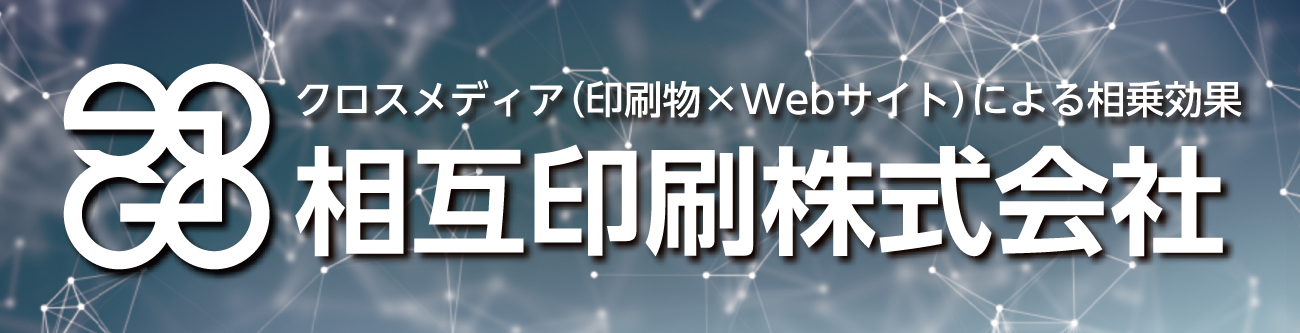酪農と文学 連載3
戦争における食糧の調達と輸送は勝敗を決する重要なポイントになることはまちがいない。まして海戦ともなれば一層の困難がともなうでしょう。一体日本海海戦では酪農産品はどのような姿で登場したのでしょうか。ロシア側の描いたそれと、日本側とを読み比べて紹介します。
バルチック艦隊の潰滅―ノビコフ・プリボイ 著アマゾンで検索
坂の上の雲-司馬 遼太郎 著アマゾンで検索
牛達の目に涙 艦底で産乳止

フィンランド湾を出港し極東の島国まで1万8千浬、大小40数隻からなる艦隊、1万2千の乗組員、まさにロシア海軍の総力をあげた大移動となったわけですが、これらの食糧や燃料の積み込みや港、港での確保は「苦難の航海」以外の何物でもなかったわけです。戦艦オリョール号に乗った作者ノビコフ・プリボイはルポタージュ文学形式の先駆といわれるこの作品でこの船艦への食糧の積み込みを次のように記録しています。
『(前略)艦の中は大騒ぎだった(中略)――陸上の倉庫から品物の受け渡しをしなければならなかった。樽詰めの塩肉、ブリキ缶にハンダ附けした牛酪、オートミール、塩、砂糖、麦粉。こんなものをすっかり開いて蔵(しま)うので、戦争のような騒ぎだった(後略)』さて、ここに書かれた〝ブリキ缶にハンダ附けした牛酪〟とはああバターなんだなと考えます。しかし、バターひとつとっても1万2千人分のしかも数ヶ月を計算して一体どれだけの分量が積み込まれたのかそんなことは書かれてはいないが、いざ決戦の頃は底をついていたことはまちがいない。司馬遼太郎の「坂の上の雲」では造船技師ポリトゥスキーが本国の妻に送り続けた手紙を引用、次のように書いています。『(前略――考えてみればノシベを出て以来すでに20数日間大洋の上をただよって1度も寄港せず、新鮮な野菜や生肉も尽きようとしていた。「わが提督の食卓にさえ、すでにウォトカ、生肉、コーヒーなどがなくなっていた」と、ポリトゥスキーは書いている』艦隊の司令長官(ロジェストウェンスキー)さえ肉食を欠く日々となればバターなど残ってないことは確かに思えます。しかし、航海の最初の描写を読めば朝食にバターが十分配分されていることがわかる。再びノビコフ・プリボイの作品から『半時間たてば朝食だ。てんでに自分の分だけのバターを受け取る。パン3フントだから余るぐらい(後略)』と書いているように〝てんでに自分の分だけバターを受ける〟というくらいだから水兵達はいるだけ食器に運びこんだのだろう。ロシア兵全てが勝利を確信してはいなかったでしょうが、バターの配分1つにしても戦況を知る目安になりはしないだろうか。
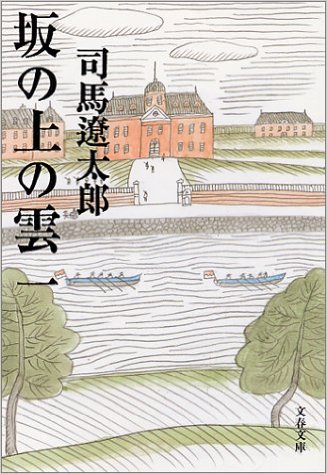
さて、この2作品を合わせれば小説としては大長編ですが、両作品を読んで気になったのは初めから積み込まれたり、途中で補給された牛達のことです。先ず「坂の上の雲」から『(前略)石炭袋の堆積のすきまごとに、この艇の食糧である牛が肩身をせばめるように息づいていた。牡牛もいたし、牝牛もいた。犢(こうし)までいた。牝牛は乗組員に牛乳を提供すべくのせられていたのだが、波涛による動揺のためどの牝牛も乳が出なかった。牛たちは、排泄物を容赦なく甲板に流した。そのたびに水兵や主計兵が清掃した。』まったく冗談ではありません、こんな環境で乳牛が〝乳〟を出すわけがない。出すのは〝血の涙〟だけでしょう。
一方、「バルチック艦隊の潰滅」にも随所に食肉としての牛の補給描写が出てきます。マダガスカルでの牛の積み込み記録は.3ページにも及びますが『われわれは16頭の牡牛と2頭の牝牛を積み込んだ(中略)軍艦の左舷側へくる迄に、どのくらい牛は困惑しただろうと私は考えた(中略)牛は、眉間をハンマーで撲られて咽喉に包丁を突き込まれる日が、遠からず迫ってくるのだが、それでも自己の全存在をもって死を感じているのだ(後略)』艦隊はさらに進みホンニヘ湾での積み込み描写は2ページもある。
『(前略)みんな牡牛で、1頭だけ牝牛だったが、こいつは肋骨が1本々々見えるぐらいやせていた。何か病気があったらしい。とくに角艦に乗せられて以来、殆んど乾草を口につけなかった。家畜係の水兵が一生懸命骨折って、小屋から引き出して兵員の残パンを食わそうとしたが、――やはり駄目で、日増しにやせて行った。大きな黒い、いくらか愚かしいが、実に柔和なその眼には、死の悲しみが溢れていた。(後略)』
撃沈された船艦とともに日本海の夕暮れの水面から悲しい叫び声をあげて、海の藻くずと消えていった家畜達の描写は胸に迫る悲哀が満ちみちている。
(次回は日本海軍がでてまいりましたから、ファン・カッテンディーケの「長崎海軍伝習所の日々」等を中心に異国人の見た記録を紹介します。なお、今回は都合により10日号に掲載しました。)
本連載は1983年9月1日~1988年5月1日までに終了したものを平出君雄氏(故人)の家族の許可を得て掲載しております。