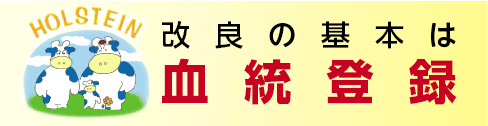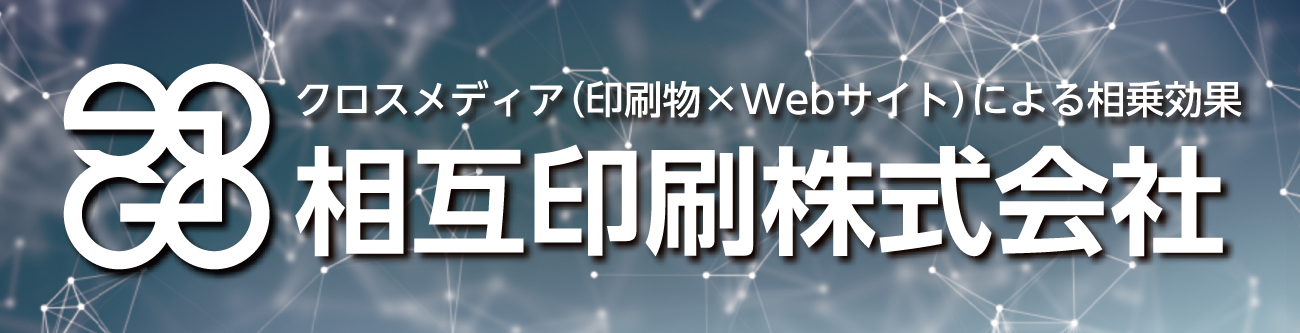酪農と文学 連載33
もし、あなたの家のバルククーラーの中に、生きていた猫や、ドブねずみが、作為的に誰かの手で投込まれていたならば、あなたならどうしますか?このフランスの作家フィリップのコントに登場する赤毛の大男はバター作りのための攪乳器に仔猫を投げ入れ、平気で仔牛の商談を続ける残忍な男として描かれています。手づくりバターの名人の酪農家の奥さんは、この所業に怒りを爆発させますが、考えぬいたあげく痛快極まる復讐劇を演じ、成功します。読む者には胸のつかえがおりるような気分です。常識はずれの肉屋(牛の仲買人)と酪農家の奥さんの闘いを描いています。救いは殺人ではないことですが……
バターの中の猫 ―朝のコントより―フィリップ 著アマゾンで検索
攪乳器に猫投入 酪農夫人の復讐

バター作りの攪乳器の中に〝猫を投げ入れる〟そんな残忍な男を描いた作品もめずらしい。
酪農家と組んで仔牛を買い入れ、自営の肉屋で町の人々に肉を売っているのを商売とする、この男の風ぼうを作者は次のように表現している。
『肉屋のボワイヨーは背が高いだけでなく、でっぷり太ってもいた。彼は町の中で幅を取った。その図体だけでも遠方から目につくのだが、おまけに色つきときていた。肉屋は赤かった。髪の毛は、赤毛のひとの髪の毛なみの赤色なのだが、頬ぺたときたら、似ているものはただ火だけだった。(後略)』と。
要するに、太って、背が高く、赤毛で赤ら顔のプロレスラーのような男として描かれています。
従って、風ぼうだけでなく常日頃の食生活も、真っ赤な牛肉をしかも生で好み、血のような色のブドー酒を、大量にしかも、イッキに飲み干す、そんな調子の肉屋というわけです。
だから、彼が納屋のそばを通ると「近よっちゃいけない。わらがはいっているんだ。」と村人がさわぐ(納屋に火がつくから!)という位だから、肉屋の体つきや、その風ぼうから生み出す全体的なふん囲気は、わかろうというものです。
さて、ある日この肉屋、酪農家のルグラン氏と仔牛の買いつけをとり交わしていたので、ルグラン家を訪れ仔牛を引きとろうと出かけた。しかし主人はする。ルグランの奥さんが対応するが、畑仕事に出かけた夫を呼びに行く。
ルグランの奥さんは、この地方でも有名なバター作りの名人です。今日も1人静かに攪乳器に向かってバター作りに精を出していたが、仔牛の取引きとなれば、これは夫の仕事。肉屋を待たして、ちょいと畑へ夫を呼びに行く。
部屋に1人残された、この肉屋、待つ間の〝暇つぶし〟ができない。赤ブドー酒でもあれば別だったが。
何か激しく動きをとっていないと落ち着かない人間、じっと耐えることを知らぬ〝火の男〟肉屋。
何を思ったか、バター作りの攪乳器に親猫から仔猫をひき離すようにしてほうり込んでしまった。普通の性格の人間ならば、バター作りの攪乳器の中に生きた猫をほうり込むなど、実行できるものではない。
しかし、この肉屋は待ち時間を、こうしてつぶすことによって落ちついて、ルグラン氏がもどるのを待ったのです。普通の神経の持主でないことがおわかりでしょう。
さて、夫のやりとりが終わって馬車につまれた仔牛を見ながら、酪農家のこの奥さんは、こう文句を口に出す。
『今まで飼っていたものを、こうやって肉屋さんにわたすのは、やっぱり悲しいもんだね。』この奥さんは、自分のところの攪乳器の牛乳の中へ自分のところの仔猫が〝投げ込まれ〟息たえているのもしらずに―。
猫の入った攪乳器がいつもの通り正常に動くはずもないのに……。バターをこねている最中に奥さんは異変を感じとるのだ。『別に雷も鳴らねば雨も降らなかったのに!わたしのクリームは、まるでかわってしまったようだ!』と。
いつも通りにならないバターに向かって奥さんはさらにヒステリックにわめく。『こんちくしょうめ、きさまなんかにまけてたまるか!』
妻のけんまくが、なんともすさまじいので、夫はバター作りの部屋に顔を出す。
攪乳器に何か黒いものが見える。奥さんが思いきって手を入れる。奥さんは3度叫んだ。
『(前略)はじめは恐怖の叫びで、これは攪乳器の底にあった、なんだか大きい、べとべとしたものをつかんだときの叫びだった。第2の叫び、これはそいつを引っぱり上げたときに立てた。そして第3の叫びは、こいつが1番鋭かったが、これは仔猫を明るみへ引きずり出したときに立てたものだった。』
酪農家の夫婦が、恐怖と怒りに燃えて不思議はない。いずれにしても犯人は肉屋であることでは、すぐに意見が一致した。
議論のあげく、夫は2キロのバターがもったいないのでそのまま市場に出せ、というが、奥さんは断じてそんなことはゆるされない、と。
奥さんは怒りと、くやしさをのりこえて、静かに、しかも、もっとも効果的な逆襲の方策をねる。
さて、次の日の〝市の日〟に奥さんは2キロのバターを持って肉屋を訪れる。(肉屋の亭主が居酒屋でいっぱいやっているのを、しかと見届けてからです。)
そして、肉屋の女房に「ご主人の注文です」ということで、しかも値段も高くしてさっさと置いて帰って行く。値上げ分は〝仔猫の代金ダッ〟とばかり。
ほろ酔い気分で帰ってきた肉屋は、事情を知って怒り狂う。ルグラン一家を皆殺しにする勢いで―― 紙数の都合で、肉屋が怒り狂う描写は紹介できませんが、想像はつくと思います。
しかし、肉屋は復讐出来ません。怒りにふるえながらも、なぜか1人寝部屋にとじこもって、さめざめと泣くのです。
太い太い指の間から、大粒の涙を、ぽと、ぽと、ぽと、とこぼして……。
本連載は1983年9月1日~1988年5月1日までに終了したものを平出君雄氏(故人)の家族の許可を得て掲載しております。