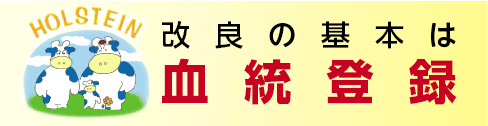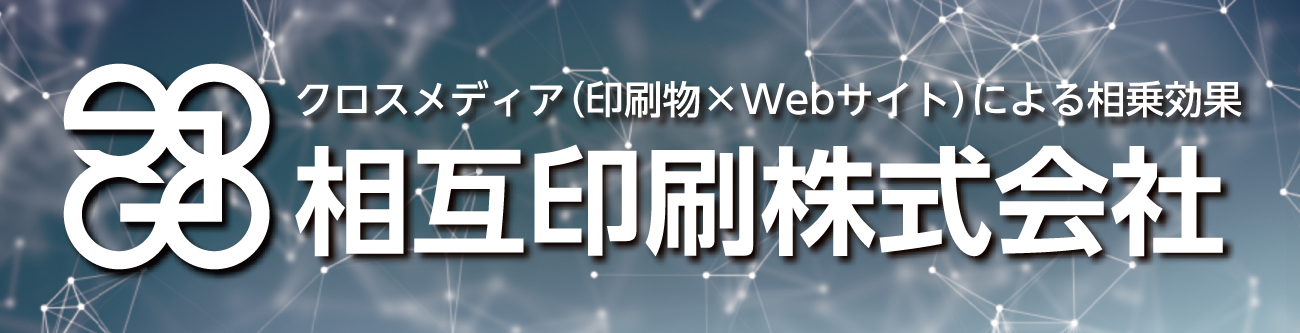酪農と文学 連載7
今回はアイスクリームの登場です。ハーマン・ウォーク作の「ケイン号の叛乱」はピュリツァ賞を獲得し、アメリカでベストセラー、海外12カ国語に翻訳された戦争小説です。生と死が裏合わせの極限にあるのが戦争ですが生と隣り合わせに存在するのが食べ物ともいえます。作者はこの小説の中でアイスクリームを使って生と死、生と食といった問題に迫ろうとしています。チーズは携帯口糧の中にはいっても、アイスクリームは少々無理でしょう。しかし、それだけアイスクリームはなんとなく平和の証しと考えられます。
ケイン号の叛乱―ハーマン・ウォーク著
アイスクリームは平和の象徴?
この小説は実在する軍人や人物をモデルにしたものではない。フィクションである。古バケツに4本の煙突といったオンボロ掃海駆逐艦の太平洋戦争を背景にした海戦記の形で構成されていますが、要はアメリカの海軍の巨大な近代組織の一部としてうごめく、ケイン号の艦長(軍人の悪いところが集中したような無能で臆病なクイーグ艦長)をはじめとして、卑劣なインテリのキーファー大尉、主人公のウィリー青年仕官のその人間的成長などをからませて、恋愛、海、戦争、叛乱、軍法会議などの展開は作者ハーマン・ウォークの確かなるヒューマニズムを感じさせる小説です。
作者はこの小説の中でアイスクリームを重要な要素として登場させ第5章「叛乱」の中で「死とアイスクリーム」の小題までつけている。
海兵隊が日本軍と血みどろの上陸作戦を展開し、砂浜に人体が吹きとんでいるのを横目にこの掃海駆逐艦の士官達がアイスクリームをたべているが、主人公ウィリーはこのことがやりきれず、ついに叫びだすが周囲の士官は当惑気味なのです。 チョコレートソースをたっぷりかけたアイスクリームは生の証しなのか、主人公ウィリーをとおして次のように描写しています。
「(前略)ウィリーは、昼食のさい、ふとしたことから心の均衡をうしなってしまった。彼が、ちょうど、アイスクリームの上に濃いチョコレート・ソースをかけようとしたとき、これまで一度も聞いたことのないような、天地をゆるがす大爆発が起った。あまりにも猛烈なひびきだったので、銀の盆皿とクリーム入れのグラスが、カタカタ鳴った。風圧が、顔の皮膚に、感じられるほどだった。」
そして主人公の激情はさらにたかまっていきます。「ウィリーは、しばらくの間、じっとこの大爆発を見まもっていた。におうような、なまあたたかい微風が、顔のあたりを撫でていった。ジョーケンスンは食べかけの肉を、むしゃくしゃ噛みながら、肩で息をしていた。やがてウィリーは自席にもどって、うまそうにチョコレートで彩ったアイスクリームの小山を、スプーンですくった。そのせつな、自分はアイスクリームを食べているのに、数千ヤードしか離れていないナムールでは、海兵が吹っとばされているのだ、という思いがこみあげて、居ても立ってもいられなくなった。(中略)この思いは、石臼のように心の中をきしみはじめた。」
この小説は艦長への叛乱とその軍法会議が大きなウェートをしめているが、戦争における〝生と死〟をこれらの箇所でアイスクリームという媒体を通じて浮き上がらせている。
肉を食べ、食後のデザートのアイスクリームに舌づつみをうつ人間、海岸で爆風で地上高く肉片と散っていく人間、作者は冷徹な筆致で描写する。
部下に叛乱まで起こさせてしまうこの気の小さい暴君艦長クィーグは、やけにアイスクリームが好きということになっておりアイスクリームと死との対比の前にさりげなく小説構成上の伏線となってでてきます。
「クェゼリン侵攻作戦がはじまらないことから、クィーグ艦長はにわかに元気がなくなって、影がうすくなった。(中略)士官室へは、食事にもぴたりと来なくなって、もっぱら、カエデシロップかけのアイスクリームしか食べようとしなかった。大量のアイスクリームが、いつも、盆の上にのせられて、艦長室に運び込まれた。」
また、次の描写は〝はめ絵〟との組み合わせで艦長の精神的異常さがうかがえます。
『艦長は机にむかって、片手で、スープ皿のアイスクリームを食べながら、空いた手では、はめ絵の各部分をつきあわせていた。「オーケー。マリックに、ここに来るように言ってくれ。それからウィテッカーにアイスクリームの大盛りをもう1皿と、コーヒーを持ってくるように伝えてくれ・・・・・。」』
アイスクリーム伝々による作者の意図は伝わるが食後のあと、しっかりとアイスクリームが食べれるならば、それは幸せで平和な主張だといえないでしょうか。
本連載は1983年9月1日~1988年5月1日までに終了したものを平出君雄氏(故人)の家族の許可を得て掲載しております。