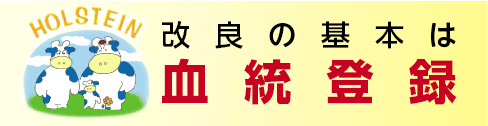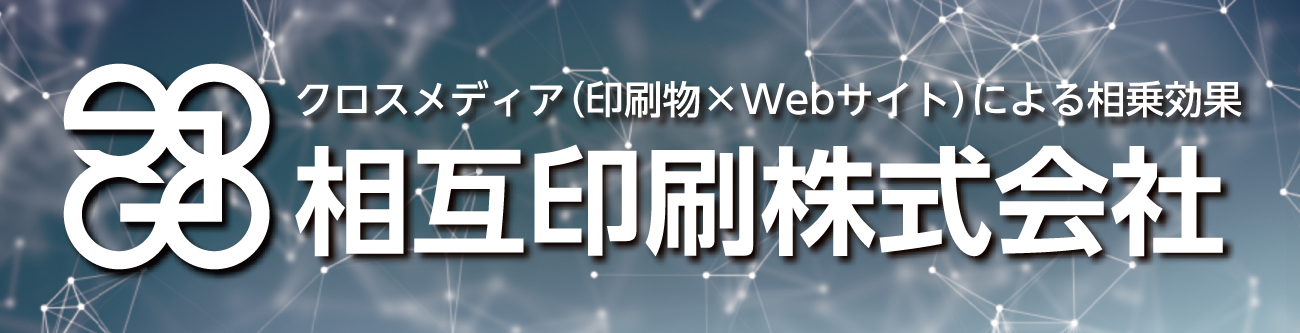酪農と文学 連載21
今回は乳牛の屁(へ)の後というわけではありませんが、牡牛と熊の死闘を紹介します。この久米正雄の熊という作品は童話で北海道の友達が訪ねてきて近所の子供に熊にかかわる話しを2つ聞かせていった、という形式をとっています。童話ですから死闘ではなく熊と種牛のけんかということですが、熊の腹がズタズタにさけて種牛が勝つわけですから、まちがいなく死闘といえます。昔から〝牛の一突き〟などといいますが、妙な例えは抜きにして童話ですから牡牛がいかに闘ったかわかりやすく表現しています。それにしても牛の角はかなりの武器ですから要注意です。
熊(童話) 久米 正雄 著
熊突き殺す牡牛 死してのちやむ
北海道の牧場である日いつも放牧させている牡牛が日暮れになっても戻ってきません。
そこで牧夫さんが牧場のあちこちを探しまくったところ驚いたことにわが家の種牛が熊とにらみ合っている。
牧夫さんは足がすくんでしまって動けない。ということはこのにらみ合いがいかにすごかったかの証明です。
牧夫さんはようやく立木のかげに身を寄せてガタガタふるえながら見ることになるわけです。
作者は牡牛がいかに戦闘体性をととのえたか次のように表現しています。『熊と牛とは猶(なお)も永い間睨(にら)み合っていました。けれどもその間に、牡牛は後足で土をしきりに掘って、自分の足場がうまく据(すわ)るように、土に凹(くぼ)みを拵(こしら)えました。そしてそれが出来上ると、どっかとそこへ足を折って坐り、身をしずめるようにして、熊の方の近よるのを待ちました。』
足場を作り、足を折って身をふせる本能的な守備体形は自然に出てくるのでしょうか。赤く血走った目と低い姿勢、熊のほうがいらいらしてきます。静と静。しかし熊は待ち切れません。ついに、先に動きました。牡牛の方へ、ジリッ、ジリッと。
今度はわずかながら動と静になるわけですが、そこから次はやはり文章を読んでいただくほうが適確に死闘のはじまりが伝わってくると思います。
『彼等はもう三尺ほどを隔てて、向かい合いました。がまだ熊は襲いかかりません。牛も黙っています。こうして、また5分間ほど睨み合いました。まるで2匹の様子は、はちきれるほど力が這入(はい)って、しかも林のように静かなのです。やがて熊は思い切ったように、奮然と後足で立上ると、その右手を牛の左の角へぐいとばかりに掛けました。が牛はまだ動きません。暫(しばら)くすると、今度は熊がその左の手を牛の右の角へぐいと掛けました。』
自分の角に両手をかけられた時牡牛の気持ちはどんなだったんでしょうか。恐怖でしょうかそれとも「しめた!」と思ったのでしょうか。誰にも理解できませんが、まの当りにこれを見ている牧夫さんの気持ちは人間ですから理解できます。こわいもの見たさ、興奮、わが家の種牛への応援、いずれにしても緊張の連続だったことにまちがいないでしょう。
さて、チャンス到来、牡牛は一転して動に転じます。『するとそのとたんに、牛は待っていたと言わんばかりに、全身の力を角に集めてぐいと熊の腹を突(つ)き上げました。ふいを食(くら)った熊は、その角を避ける余裕もありません。一突きつき上げてしまってからは、もう何と言っても勝負は牛のものです(後略)』と。
あとは熊がいかにもがき体勢を立て直そうとしてもだめなのです。突いて、突いて、突きまくって大木の根元まで押し進むわけです。
それからのすさまじさと、悲しい情景はどうでしょう。そうです、大木にすざまじい勢いで押しつけた牡牛は一歩たりとも動きません。これ以上に大木をもなぎ倒すほどの力はありません。しかも長い間続ければ精も魂も使い果すはずです。勿論熊は息たえております。腹をズタズタにされて。
牧夫さんがしばらくして近づいてみると、牡牛もまた死んでいたのです。
<この作品は童話作家の坪田譲治が編集した赤い鳥(大正から昭和にかけて発刊された童話集)傑作集の中の1編です>。
本連載は1983年9月1日~1988年5月1日までに終了したものを平出君雄氏(故人)の家族の許可を得て掲載しております。