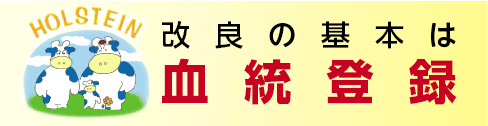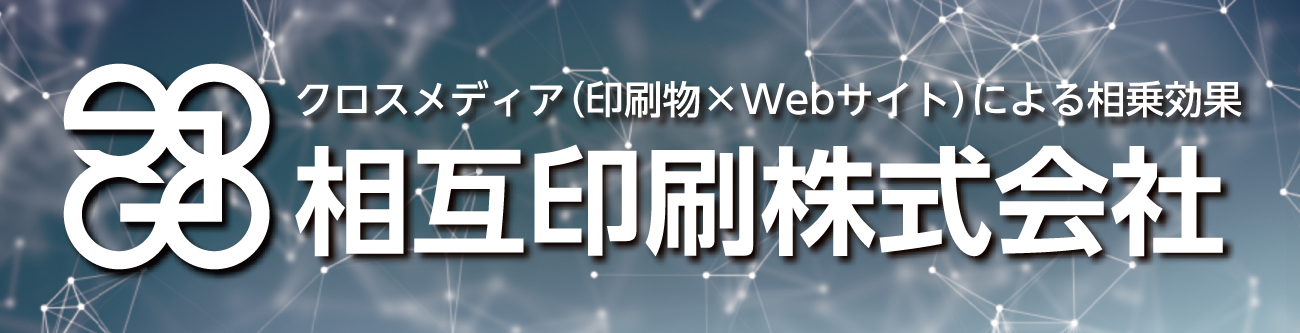酪農と文学 連載39
いままで、いろいろの東西の作品から、牛乳、乳製品にかかわるものを取り上げてきましたが、チーズという乳製品を使って、作品の中心となる情念の世界を表現した作家はおりませんでした。このフランスの天才作家は17才の時にこの作品を書き、20才でさっさと死んでしまいました。当然この作品は17才の少年の作品であること、人妻と少年の不倫物語として大きな反響をよんだのですが、筋は何もむずかしいことはないのに、作者は愛を中心とした世界をチーズにたとえて書出していることです。従ってその部分はむづかしいのですが、愛の世界がチーズとはいろいろと考えさせられます。
肉体の悪魔 レイモン・ラディゲ 著アマゾンで検索
チーズは愛なり 甘く悲しい芳香
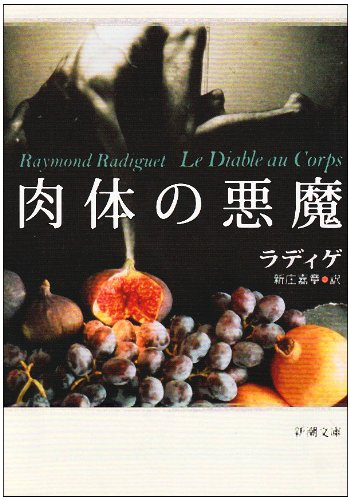
学乳の供給のパイを広げなければ、というのが、酪農、乳業関係者の願いである。この啓蒙ことばが”頭脳明晰な児童を育てる〟ということですが、作者のレイモン・ラディゲという人は17才でこの作品を書き、大きな反響をよんだ。そして20才で死ぬ。いわゆる神童である。
この作品の発表後、作品批判等に答えた中で、作者は「神童なんてどこの家庭にもいるし、時がたてば凡児になる」といい切っています。
作者は赤ん坊の頃から多分、牛乳、乳製品にはぐくまれて育ったことはまちがいない。そのため、頭脳明晰な神童になった、というのは短絡的な理解ですが、この作品の始めの部分に主人公が、その時代(第一次世界大戦中)の混乱や、少年の持つ複雑な情感などを含めて、自分をネコにたとえながら、とりまく社会と環境と戦争をガラスにたとえ、そのガラスの中にチーズがある。ガラスの中のチーズはとりもなおさず、甘くて、せつない恋と愛欲をあらわしているのです。
私がいいたいのは、少年が戦争によって打ちくだかれたガラスをぬけて、追い求める少年の情愛の周辺の表現を〝チーズ〟と言っていることです。
学乳と神童とチーズという乳製品の組合せはムリな組み立てですが、少なくとも、作者が作品の主体を占める情愛の世界をチーズにたとえたことは、幼児からの牛乳や乳製品との接食と無縁とはいい切れない、と思います。
さて、かんじんの作品の冒頭のチーズで比ゆした、〝さわり〟の表現は次のようです。
『僕にあってはガラスの覆(おお)いごしにチーズを眺めている猫のように、すべてが現実として映った。しかし覆いは存在するが、覆いが壊(こわ)れると、猫はそれに乗じる。たとえそれを壊したのが主人であって、そのために手を傷つけたとしても。』 少しこむづかしい表現ですが、いよいよ少年は人妻との不倫におちいる以前の心のゆれ動きを、こう書いています。
『ほんとうの休暇がやって来ても、どうせ終始同じである僕としては、それはたいして変わらなかった。あい変らず猫は硝子の覆いを透(とう)してチーズを眺めていた。が、そこへ戦争がやって来た。それは硝子の覆いを粉砕してしまったのだ。主人どもが他の猫を鞭打(むちう)っていたので、この猫はすっかり有頂天だった。』と。当然ガラスがこわれれば、猫は中のチーズにかじりつきます。
まあ、17才の少年が、人妻と愛欲をたかめて行くのですから。周囲は勿論、本人達の心理も、あるときは乱れに乱れたりして、せつなく、甘く、物語は進んで行きますが作品中、出征中の夫のるすに人妻のところに通いつめる主人公が、朝がえりの時、牛乳配達人とでくわすくだりが出てきますが、1人ははだしでクツを持ち、一人は早朝労働で牛乳ビンをもち、ばったりとでくわすところがあります。
『朝の5時になると、なるべく音をたてないように僕は靴(くつ)を抱(かか)えて降りた。それは階下(かいか)ではくためだ。ある朝、僕は階段で牛乳配達とすれ違った。彼は牛乳瓶(びん)を手にしていたし、僕は靴を持っていた。彼は変な笑いを浮かべて、お早よう、といった。これでマルト(主人公の恋人)も終わりだ、彼はJ(恋人の住んでいる所を主人公はJと呼んでいる)…中にいい触(ふ)らすだろう。(後略)』
猫(少年)はチーズをたっぷりとたべた。甘かったけれど、どこかほろにがい、そしてせつない味がしないでもない。牛乳配達が商売なら、配達人はチーズの匂いはかぎわけられる。
この作品は少年と若い人妻の恋愛小説ですが、人妻は妊娠し、産後の肥立ちが悪く死んでいく。勿論子供は夫の子ではなく主人公の子という、悲劇の設定です。
天才作家が、少年や少女(人妻)の愛を中心とした世界を”チーズ〟にたとえたことに、限りない愛着を覚えます。
(「現実のチーズがそのまま見えている。しかし、間にガラスがあって、どうしてもチーズに手が届かない。ガラスが1度こわされれば、ネコはチーズをくわえて逃げ出します」=三島由紀夫の「わが思春期」より)
本連載は1983年9月1日~1988年5月1日までに終了したものを平出君雄氏(故人)の家族の許可を得て掲載しております。