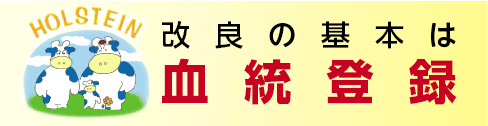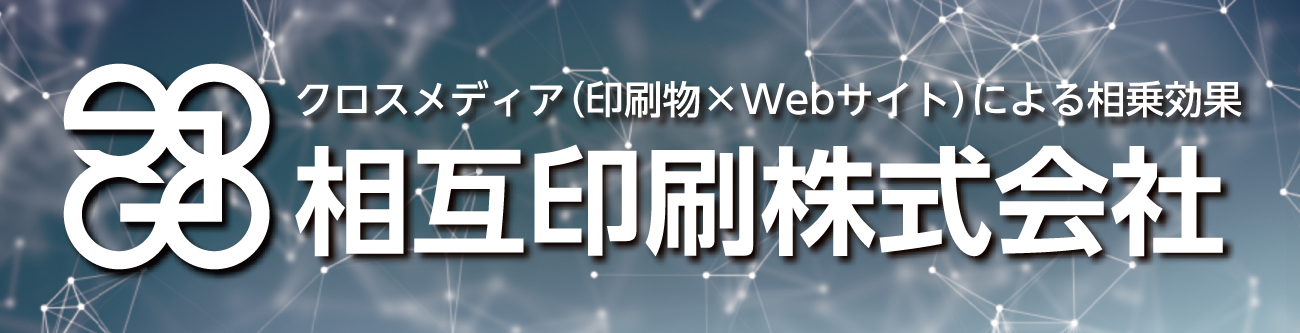酪農と文学 連載8
アメリカが生んだ偉大な作家ヘンリー・ミラーの作品には、いたるところに乳製品を中心、特にチーズ、バターを比喩した表現が目につきます。作者は文学者としての修行時代は長く食うや食わずのパリ―時代等も経験していますが、そうした食べ物への執着は作品の中で力強く生きづいています。今回は「南回帰線」のみをとりあげて紹介しますが前々回に紹介したヘミングウェイの作品に登場する乳製品とは一味ちがった扱い方をしています。
南回帰線―ヘンリー・ミラー 著アマゾンで検索
世界は大チーズ私はその一片だ

この作品にとびだしてくる牛乳、乳製品、とくに乳製品はただの乳製品ではない。あるところではチーズが作者の世界観にもかたがわりすれば、一方では売春婦とのやりとりの印象づけに使われたり、いたるところにてっぽう玉のようにとびでてきたりします。
次の文章は「南回帰線」の作品の中の一部ですが、自分自身をチーズの一片として表現しています。もちろん、たったこれだけの表現にこの偉大な作家を理解することはとうてい不可能であり無謀な試みだと思いますが、この世の中を大きなチーズにみたてて、自分自身はその微小な一片にすぎないといい切っている以上、またこのように比喩的にチーズをとり上げていることなどからして是非ここに紹介せざるを得ない。
また、この作品(作者の全ての作品)は筋書きらしいものは何もない。従って誰とだれがどうなってといった外面的なものは期待できない。この作者の作品ほど作者の魂といっしょになって、やみの中をともにくぐりぬけて、人間の根源的なものに迫ろうとしないかぎり理解できない。
さて、作者ヘンリー・ミラーは次のように書いています。
「(前略)私はひとりになったことがなかった。とりわけ、自分ひとりでいるときには、そうでなかった。つねにだれかといっしょにいるような気がした。そう思いきめてしまったわけではないが、私は世界という大きなチーズのごく微小な一片のようなものであった。もちろん私は隔絶されて生きていたわけではないし、私自身を大きなチーズだと考えたこともなかった。」と。
次にロシアで詩人の夫をもつ人妻とセックスをする描写があるが、この中で作者はその夜の性の表現をリンバーガー・チーズにたとえています。読者はリンバーガー・チーズがいかに強烈な匂いをもった個性的なチーズであるかご存知でしょうから次の文章をお読みになればその雰囲気はご理解いただけるでしょう。
梅毒云々の表現がありますが、これは主人公が友人からその人妻は梅毒かも知れないゾ、とおどかされた後のことですが、主人公は「私はそうやすやすと梅毒にかかるわけはない」との決意をもっていどんでいるところが愉快ですが梅毒人妻(?)とリンバーガー・チーズの対比はなんとも異様な感じですが、それだけ個性派のチーズということでしょう。
『(前略)私はあくびをした。梅毒かどうかしらないが、まったく舌のとろけるようなリンバーガー・チーズだったーとひそかに思った。(中略)私が彼女に決定打をあたえて試合の幕を閉じたとき、私は、ひそかにひとりごとをいったものだ―「やれやれ、たっぷりとリンバーガー・チーズも食ったし一眠りするか・・・・・」』
この作品には多くの比喩がでてきます。牛乳、乳製品の消費拡大を叫びつづけるわれわれにとっては気になる〝語い〟もあるわけですが「私は一片のチーズ」といった作者に敬意を表して列記します。
「(前略)それは虫食いだらけのチーズよりも、もっとひどく腐りはてていた。(後略)」
「(前略)大きなチーズのかたまりに食らいついたネズミのように、下へ下へもぐる(後略)」
「(前略)ミート・ボールは腐り、コーヒーは味が変わり、バターは悪臭を放っていた。(後略)」
「(前略)淫乱症のローラは欲情をさらけ出して、雌牛の尻尾のように体をくねらせながら、ルンバを踊っていた。(後略)」
「(前略)黄金色の二十日ネズミが百万匹、目に見えぬチーズを齧っている。(後略)」
「(前略)まるでネズミが大きなチーズをどん欲に齧るように、周囲の渾沌(こんとん)のなかに食いこんでゆくのだ。」
「(前略)おまえの子宮のなかで燃えている太陽をみつめる。あの牛乳のかたまりと、ぱちぱちいう騒音は、いったいなんだ?」
ざっとこんな表現で作品全体に現れてきますが、これはこの「南回帰線」だけからで、ヘンリー・ミラーの全作品には多くの牛乳乳製品、牛肉を比喩した言葉が無数に登場します。
本連載は1983年9月1日~1988年5月1日までに終了したものを平出君雄氏(故人)の家族の許可を得て掲載しております。