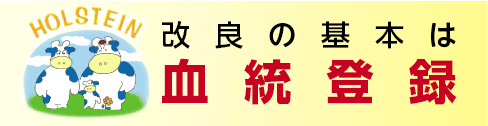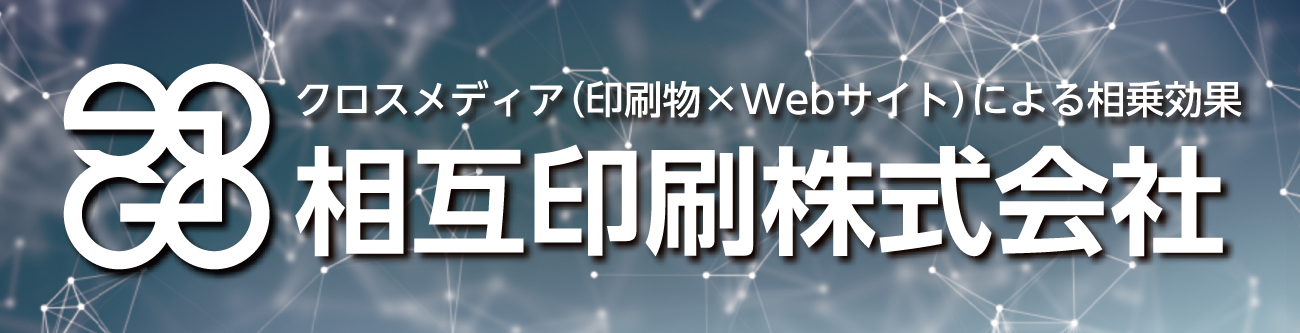後継者、酪農女性に贈る牛飼い哲学と基礎技術
連載19
死を招く乳房炎 二次的災害もたらす陰性菌 ワクチン治療が困難な上に 軟膏注入でショック死も
近年、グラム陰性桿菌(環境性大腸菌類コリフォーム)による「えそ性・甚急性乳房炎」で急死する例が増加している。高泌乳を期待していた優秀牛が分娩後1~2日で症状が甚急に悪化し、治療を施す余裕もなく死亡する。経済的損失のみならず、酪農家の精神的打撃も甚大である。
乳牛の死廃事故のトップは乳房炎で、全体の2割を占めつつある。次いで関節炎・脱臼がそれぞれ1割未満、酪農家が現在でも恐れを感じている産後起立不能は死廃事故の第4位(8%)で、次に第四胃変位が追随している。
この死廃事故要因の上位5位のうち、治療する間も持てずに急死するのは「えそ性乳房炎」だけで、異質な疾病である。
北海道農業共済直営診療所がグラム陰性桿菌の過半数を占める「大腸菌性乳房炎」の治療実態調査結果を報告している。
それによると、年間2万8千頭発生し、その10%にあたる2800頭が死亡しており、加入牛の0.38%に相当する。
全国各地のデーターからグラム陰性桿菌乳房炎の原因菌の内訳は、50~60%が大腸菌、5~13%がオガ粉が元凶のクレブジェラ菌、3~17%が緑膿菌(シュードモナス)となっている。
このデーターを参照すると、大腸菌で0.38%が死亡していることから、グラム陰性桿菌(環境性コリフォーム)全体では0.7%にあたる。例えば成牛140頭規模の場合、毎年1頭はえそ性乳房炎で死亡していることになる。
また、北海道の報告では、53診療所で大腸菌性乳房炎を完治させた割合が66~93%と幅があり、治療に至る診療回数は平均5回で、死亡は転機が早いだけに診療回数は少なかった。
1970年のペニシリン牛乳規制の開始当時は、グラム陽性桿菌(破傷風菌と同類のガスえそクロストリジューム菌)によるえそ性乳房炎が散発した。難産や後産停滞牛が多く罹患し、患牛の外陰部周辺や乳房前方が浮腫や気腫を生じ、乳頭は青みを帯び、冷たく〝捻髪音〟を発し、ガスを含んだ乳汁が排除された。
幸いグラム陽性桿菌は抗生物質が有効で、さらに破傷風トキソイドなど最も安全なワクチンも完成し、効果を発揮している。
当時の「えそ性乳房炎」時代は、出荷乳にまで「ペニシリン」が汚染するほど抗生物質が乱用されたし、効果も認められていたことから食品の多くが薬漬けとなっていた。
細菌は乳中体細胞より一桁小さいが、同じ単細胞生物で固い細胞壁を持つことから植物系である。やっかいな存在になりつつある真菌(カビ)は細菌の数倍ある赤血球と同じ位の大きさである。細菌の形が球形のものを球菌(コッカス)、細長いものを桿菌(バチラス)と称し発育・増殖状態がブドウ房状のものをブドウ球菌(スタフィロ・コッカス)、また、鎖状に連なる球菌を連鎖球菌(ストレプト・コッカス)などと便宜上呼称している。
さらに、細菌細胞の細胞壁の構造上の差、つまり細菌壁の外側にさらに外膜があるか無いかが重要な問題で、抗生物質ペニシリンが有効か無効かの分かれ目になっている。
この細菌を二分類する外膜の有無を染色液で染め分ける方法をグラム染色という。この染色は紫色素で黒紫に染まって、ルゴール(ヨード)で色素定着し、さらにアルコール漬けで脱色の有無とヨードとアルコールで完全殺菌も兼用して脱色した細菌を判別しやすいように赤色のサフラニンで再染色する。赤色はグラム陰性、黒紫は陽性と染め分ける。
グラム陽性や陰性とは何か
細胞壁が外膜と二重構造になると、その外膜がバリヤーになってヨード剤の侵入を阻止したように他の薬物・抗生剤をも阻止する動きが強いため、グラム陰性菌は治療上の困難性が強い細菌である。
ちなみに、真菌は細菌ではなく、細菌を杭ずる抗生物質そのものを産生する張本人であって、亢真菌剤は数少ない。
多種多様の抗生物質の開発によってこれらに感受性の強いグラム陽性菌は耐性菌を生みながらも衰退し、抗生物質にバリヤー(外膜を持つ)を持つグラム陰性細菌がグラム陽性菌と勢力争いする苦労も少なくなって、えそ性乳房炎原因菌も陰性菌へ選手交代の時代を迎えてしまった。
さらに、やっかいなことに、外膜を有するグラム陰性菌は、菌体内に菌体内毒素(エンドトキシン)を貯留して菌体が崩壊すると、この内毒素を放出・遊離して二次的災害を招来する。グラム陽性菌は外毒素を分泌するが、先述したこの毒素を用いたトキソイドワクチンが実用化されている。
内毒素は0-157大腸菌食中毒事件でも難題とされたように、現在も積極的なワクチンは開発されていない。内毒素は毒力は外毒素より弱毒であって、日和見感染のように出産時の体調不良時に内毒素・エンドトキシンショック(=主要臓器出血壊死)及び、血管内凝固組織壊死(=DIC)を招き死に至る。
特に牛は人の幼児同様、内毒素に感受性が強く、えそ性乳病炎治療にあたって殺菌的な乳房炎軟膏の注入で細菌の崩壊を一機に生ぜしめると、内毒素ショックで死を招くようだ。
旧来のえそ性の治療時も抗菌剤の注入等でショックを経験していたが、これが治癒率を低下させている。
また、初乳中で食菌細胞の働きで生じた内毒素で起立不能・血圧低下・低体温を発症する。これを「乳熱」と考え、カルシウムを自分で注射し、下腹部の乳房を無視して死を招く。
一方、細菌とともに内毒素を物理的に排除するために30分ごとの頻回搾乳とバケツ2杯の味噌汁の経口補液で克服した酪農家がいる。
本連載は2003年5月1日~2010年4月1日までに終了したものを著者・中野光志氏(元鯉淵学園教授)の許可を得て掲載するものです。