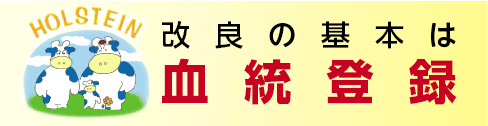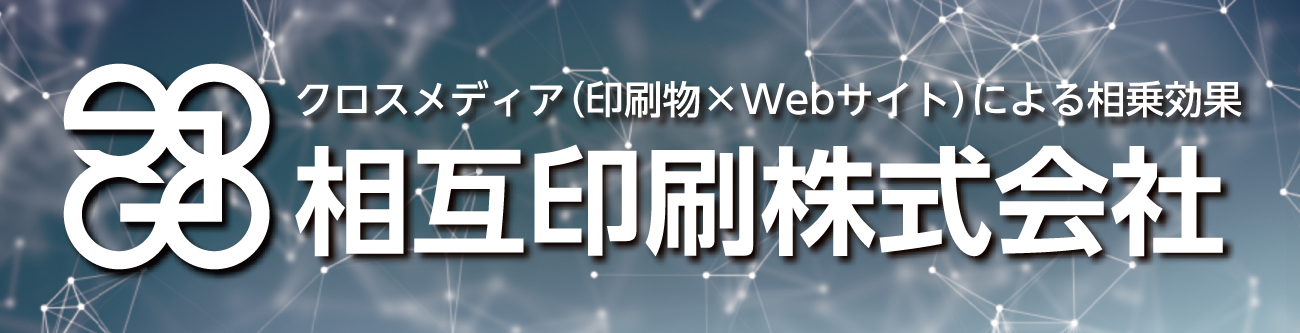後継者、酪農女性に贈る牛飼い哲学と基礎技術
連載37
そもそも畜産とは 乳価は低下、負担は増加 安全・安心は命の保障費消費者は理解しているか
桜の花も花吹雪と共に潔く姿を消し、新緑を天空に力強く広げ目映い(まばゆ)いぐらいでしょう。この連載も年末以来、生産抑制など明るい話題に欠け、少しでも酪農界が明るさ・ゆとりを取り戻さねば窒息しそうだと考えています。
そもそも、畜産は英語で「Livestock」といい、つまりは「生きたまま貯蔵しておく」ことを意味する。コロンブス時代の遠洋航海船には生きたままの緬羊を積み込んで飼育しながら逐次と殺して新鮮そのものの血液などを食することで壊血病が予防されていた。
また、畜産領域でも豚や緬羊のように生体そのものを潰して食べてしまうのではなく、「reproduction」、すなわち、「recycle(リサイクル)」と同じ意味合いを持つ単語がある。
つまりは、鶏や乳牛は、それそのものを食べる目的ではなく、卵や牛乳へ形を変身させ、本体である母体は働けるだけ生き長らえさせて循環することで人類に貢献させる。卵や牛乳を再生し続ける「繁殖」の意味が重複して畜産本来の生き方を表している。
再生産、持続型、そして循環型である酪「農業」は、あくまでも農民がその土地に立脚した経営によって、人畜が土地、すなわち自然に適合して、コンフォートにゆとりある人畜が精神的にも健康な環境を醸し出すことにあると私は考えている。
日本がアメリカとの戦争に負けてようやく平和な時代を迎えた頃、私は九州・大分県の九重高原(戦時中は陸軍の演習場で民間人は立ち入り禁止であったので、一部は入跡未踏で魅力的な自然そのものの高原だった)に出かけ、テントを張って寝込んだが、夜明け早々に牛達に目を覚まさせられた。
私は、生れて初めて九重高原で牛の放牧を目の当たりにし、牛が人懐っこく近寄ってきて、草を味わいながら私達をじっくり観察しているようだった。
その後、学生時代に各駅停車に乗って帰省する途中に、出雲山中の三瓶山の放牧場を見学した。ここでも牛と放牧地の草が絵のような調和を描き、これこそ自然界の営みであると感じた。
牛や鶏はその土地に根付いた草を気軽についばむ。牛は自然な状態で乳を搾られ、卵は開け放たれた小屋で決まった箱の中に行儀良く生み落とされていたものだ。この風景が現在も強く私を支配している。
狭い国土面積は昔も今も変わらないが、それなのにわずか数年の間に遠隔地から土地を離れて多量の牧草が工業的に原材料倉庫に格納され、牛そのものも土から隔離されてしまった。
牛乳はトヨタ方式で機械的に搾られ、土から切り離されて輸入品の加工専門となり、工業的に「re」をとっぱらって「product」つまり、製造される現況になっている。
アメリカ自動車業界で「ビッグ3」の一角を担うフォード社は、トヨタとの競争に破れてリストラがはじまっているが、構造改革に煽られて金銭がらみの「ホリエモン」騒ぎへと発展した日本社会は、いわゆる勝ち組に圧倒されてしまっている。
自然界を育み、太陽の恩恵を全身に受けて酪農家が丹精こめて生産した「牛乳」の需要・消費は、学校給食も季節がらみの春休みも重なって好転の兆しはない。ついに北海道ではバルクタンク横に大型バケツを設置して、集乳時にバケツ一杯の自家消費用の牛乳を強制的に給与。毎日のように出荷制限してきたが、この程度の出荷抑制では解決できず、牛乳を900㌧近くも廃棄したとテレビで全国放送された。
欠陥品どころか世界最高の土地の恵みである乳が父にも通ずる「父の日」の贈り物に活用されること無く廃棄されたわけだ。
畜産はベルトコンベアのスイッチを切れば生産が停止する物ではなく、もったいないから海外の食料不足国に援助物資として有効利用出来ないかと政府としても考えねばならないと、ごく当たり前の口上が大臣の口から語られた。
もし、トヨタの新車がフォードと同じ運命で生産過剰に陥ったならば、電源を切るだろう。しかし、牛乳のように産業廃棄物扱いで海底に放棄されることはない。
この牛乳廃棄報道と共に、BSE問題でアメリカとの牛肉輸入再々開の審議段階で、相変わらず政治的圧力に耐えられず、審議会である食品安全委員会プリオン専門調査委員会の半数(6名)の委員が自分の意思で辞任していたことを初めて知らされた。
初回の牛肉輸入再開時は、アメリカ大統領の外国訪問時に途中下車したという日本訪問に合わせた政治がらみの再開だったはずだ。日本酪農の現場では、国内でのBSE発生以来、牛飼い自らの生計を脅かした「肉骨粉」「農薬漬け牧草」など酪農先進国からの乳牛用輸入飼料へ厳重な監視と学習を強め、乳牛飼料の安全性を追求し消費者のみならず酪農家自身が「食の安全・安心」のために神経をすり減らしている。
国内の全頭、生まれたての赤子からトレーサビリティ(生産履歴、この場合は戸籍登録)のために大きな耳票を酪農家自らの手で短期間で全頭に装着し、国営の管理センターである家畜改良センターへ逐次報告している。
この耳票とともに、乳牛の習性として毎日決まったパターンで飼養管理されている餌の内容まで細かく毎日チェックして、その結果を全国統一で配布されたチェックシートに記載して、その記録は保存される。常に情報公開に応じられる体制がとられている。
BSE対策の対応の速さと実効ぶりには、欧米の関係者は驚き、注目を集めている。アメリカの心ない人物によるずさんなBSE検査体制の中からも無関係と公言してきたが、ついに3頭目が発見されても全頭検査を大国の拒否権発動で無視している。
これら「食の安全・安心」に対する労力とコストは全て酪農家の負担であって、だぶつく生産情況では乳価が低下する一方、コストだけは増加していることをどの辺りまで消費者は理解してくれているのか。
経済界では物価が安いデフレは危険だといいながら、安全・安心へのコストの負担増など消費に対する命の安全保障費だということも、経済界で検討してもらいたい。
アメリカは何ごとも世界をリードしてやまないが、その魂を象徴する「ビーフステーキ大国」での食品検査官のBSEへの対応振りを見ても、日本の消費者の中には、輸入国でBSEが発生しても在庫品一掃セールスには列を作って胃袋に入れるという笑いごとではない行動をとる人が存在する。それは本人の「ビーフステーキ後進性」か、もしくは、青い目への憧憬から来るのだろう。
そのレベルで日本の酪農を軽視するわけで「全頭検査は無駄」と決め付けるのは、その場限りの金銭感覚的発想である。
今になってアスベストの災害補償問題は企業の手を離れ、国が税金を使い始めたが、企業的ではない畜産を「日本は輸入に頼るべき」と決め付ける発言には警戒せねばならない。
本連載は2003年5月1日~2010年4月1日までに終了したものを著者・中野光志氏(元鯉淵学園教授)の許可を得て掲載するものです。