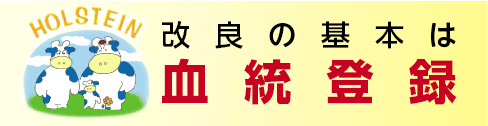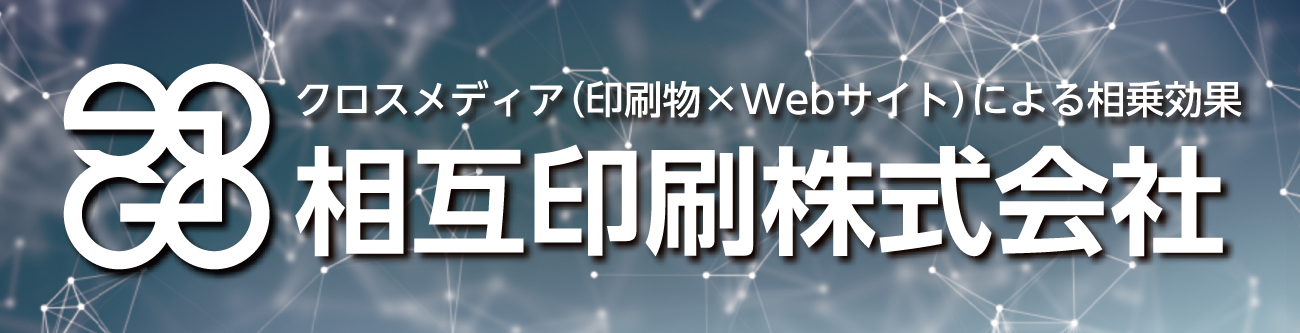後継者、酪農女性に贈る牛飼い哲学と基礎技術
連載26
広がる治療基盤 限界に来ている抗生物質治療 自己治癒力を刺激する 同毒療法に復活の兆し
10年程前からノルウェーを中心に、フィンランド、スウェーデンの北欧三国が、国際酪農連盟(IDF)の乳房炎委員会(A2)に提言している乳房炎防除方式は、旧来の米国方式と著しく異なっていることを、市川委員(日本側)が「特産畜産の研究」誌に逐次報告している。その違いとは、乾乳軟膏とプレディッピングを推奨しないこと、記録データーの重視にある。
牛群検定の組織化率は9割であり、そのデーターは、酪農家は勿論関係者すべてにフィードバックされ、乳房炎除去と種牛の改良に活用されている。
広範囲抗生物質の登場に比例して多剤耐性菌も増大し、抗生物質治療は限界に来ている。体細胞30万以下を維持するのに、日本では高細胞乳の廃棄処分に重点が移り、防除対策については疎かになっている。
この現実に、ホメオパシー(200年前、抗生物質登場以前の欧州を脅かした腸チフスやコレラの治療法である予防と自己回復力治療を主軸とした同毒療法)による乳房炎予防・治療が、ドイツを中心に関心を集め、復活の兆しを見せている。
本年3月には、日本獣医師会誌に森井氏が「日本の獣医療におけるホメオパシーの現状と展望」と題して解説報告を掲載している。
この要旨は、ホメオパシーは相補・代替医療の一つとして近年急速に見直されている治療法である。多くの経験的実績の重積でありながら科学的根拠が少ないと否定的な扱いを受けてきたが、1980年以降はEBM(Evidence Based Medicine・科学的根拠に基づく医療)の時代に、医学雑誌にもホメオパシーの臨床的有効性が肯定的に登場し始めている。
さらにEBM中心の医療の中でも患者・患畜の語り(Narrativeナレーション)に基づいた医療NBMを重視する動きが活発になってきており、これを獣医療に置き換えれば、患畜の状態を詳細に把握するため畜主との対話を重要視し、患畜の体質・飼育環境など全体像を見、発病に至る原因経過を把握し、自己治癒力(ホメオシタシー・恒常性維持)を刺激し促進させる。
そして、いわゆる3分間治療から脱することがホメオパシーを一般治療の選択肢として導入するカギとなる。これらにより、治療基盤が広がり病気と回復の理解が深まることになる、である。「うるし」職人は子供に小さいときから漆に触れさせたり、時には口に入れたりして「漆かぶれ」にならないようにするという。
近年多くの人を悩ませている「花粉症」対策も、花粉を物理的に排除することに集中しても限界がある。そこで発想を逆転換し、花粉を積極的に食べたり「花粉液」を皮下注射したりする減感作療法が行われている。
私の失敗談をしよう。乳牛の全身に波及した「イボ」を外科的に1個も残さぬよう全摘出したことがある。しかし術後まもなく患牛は絶命してしまった。止血等手技的には完璧だった。だが、化膿防止のために注射した抗生物質によるショックと、長時間に渡る手術のストレスに耐えられなかったのだ。
この事件以後、イボ退治には、ハトムギを給与したり、イボを少量採取してするつぶし生食水で注射液を作り、残っているイボに注射した。まさに「毒を以って毒を制す」の諺の通り、徐々に萎縮・脱落してイボは退散させられた。
先日、酪農協の組合長から「初乳豆腐」の味を懐かしむ話を聞きながら、初乳に対する矛盾に改めて思いを巡らせた。すべての乾乳牛に習慣的に抗生物質を注入するようになってから、私自身も初出荷の生乳に残留抗生物質反応があるのを経験している。確かに日本人は初乳を食べる(飲む)習慣を失ってはいるが、その初乳を子牛に飲ませても大丈夫なのだろうか。
一時期、初乳を初搾り時に搾り切るようになって減少した「血乳」は、産次が若くなった現在、初産牛などで見られる頻度が多くなっている。「白」乳のはずが「赤」乳では、ショックが大きく直ちに抗生物質注入を開始してしまうことは、心情的には理解できなくはない。
しかし、なぜ酪農家の手元に抗生物質の在庫があるのだろうか。人間用の家庭薬の中には、高単位の抗生物質は存在していないのに家畜には許されるのだろうか。
この血乳の治療は、2~3%ホルマリン液を1㍑経口投与するだけで殆ど一発で解決した。この療法は、古い家畜共済診療指針には記述されているのだが、ホルマリンが解剖臓器などを保存する毒薬であるためか、最近では忘れられているようだ。ペニシリンが高価で高嶺の花だった頃、患畜の生乳を皮下注射して自己免疫力、自己修復力を刺激して回復を促進していた。実際、リンゲル液よりも栄養価が高く、蛋白源による免疫療法にもなっていた。
甚だしいときは、毒血療法とまで呼ばれた、患畜の血液を皮下注射する方法も試みた。抗生物質以前の時代は、患畜の症状の変化を刻々と観察し、朝・夕の体温微差による治療効果の違いがあるかにすら配慮し、まさにワラをも掴む思いで診療したものだ。
近年、乳房炎治療などでの検温頻度や触診・乳汁検査が、デジタル計器の普及にも関わらず下がっているようで、軽視されすぎているように感じている。
次回は、欧州のホメオパシーについて述べようと思う。
本連載は2003年5月1日~2010年4月1日までに終了したものを著者・中野光志氏(元鯉淵学園教授)の許可を得て掲載するものです。