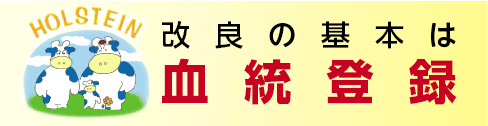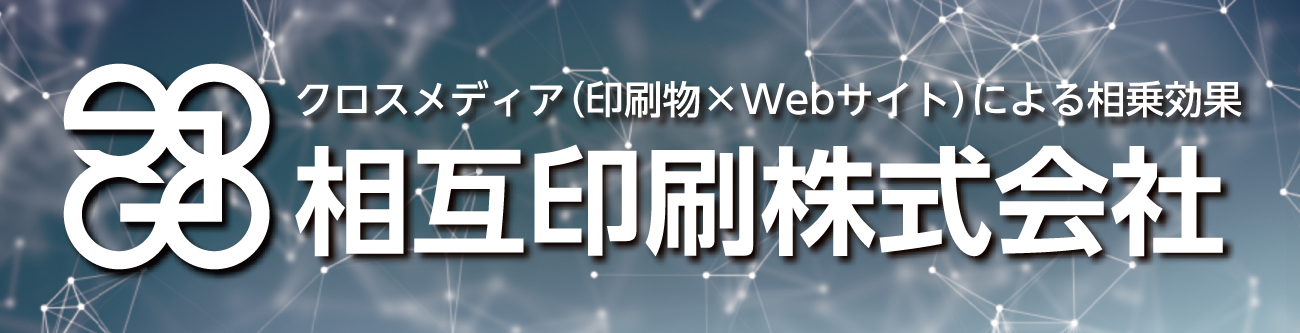後継者、酪農女性に贈る牛飼い哲学と基礎技術
連載30
子牛の扱いを学ぼう 人間の都合は子牛の不都合に 哺乳はゆっくり時間をかけて
歴史は繰り返すといわれるが、酪農界でも以前聞いたような考え方が聞かれるようになった。
例えば九州生まれの私が50年前に大分県九重町や島根県、岩手県に見学にいった「放牧」が見直され、「低投入酪農」という考えが登場してきた。
一方では喜ばしいことに酪農家の祝儀が続いて北海道から九州まであちこち見学させてもらう機会を得たが、牛舎の中いずこもアメリカ産か豪州産の輸入乾草が山積みされていた。
日本全国輸入飼料の加工工場となっている。いくらか救われたのはあちこちにヘイベーラの丸い梱包が目につくことだ。
再び国が打ち出した飼料自給率向上によって、タワーサイロなど放棄せざるを得なかった多くの酪農家にまだ回復力が残存されているのだろうか。
また、食品製造粕の有効利用で自給率向上を目指すのは、都市近郊の「一腹搾りの粕酪農」の復活を予告しているなと思っていたら、早速、乾乳はやらずに搾乳を続ける考えが復活しそうだ。
さらにかつて「千葉房州牛」は維持飼料が少なくて搾乳量は抜群だと小柄ながら良く働いたが、時代は「大量消費は美徳だ」、「牛が大きいことは良い事だ」と大型化がすすみ、牛床の長さなど耐用年数内に幾度か改造を余儀なくされた。牛体重の増大は蹄病を誘発。足から自滅し、投資もかさむ。近年はようやく大型化に歯止めがかかったようだ。
このような動きの中から、若き後継者諸君の人数は昔と比べ現在は100分の1に激減したが、酪農の先輩である爺様たちが試行錯誤しながらも牛飼い技術をそれぞれ身をもって確立して、さらにこれを前進させながら父母達が改革してきた技術の背景と現在話題にしている考え方との兼ね合いを私見を交えて紹介する。若手の諸君がさらに発展する手掛かりになれることを願ってまとめていきたい。
今回は分娩直後の子牛の扱いについて2~3述べよう。
現在の酪農家は「四変」を知らずはもぐりに違いない。ところが生まれたばかりの子牛は「四変」にならないのだろうか?初乳を出来るだけ早く(10分以内とか)飲ませることが免疫力を高めるから、また立ち上がって動き回るようになると初乳を飲ませるのも手間がかかるからと、子牛が立たず動かないうちに強制的に飲ませている。
ところが無理なお産や双子は勿論、元気が良くても早すぎる強制投与は、まだかなり羊水が四胃に停留しているから初乳を飲ませても羊水で薄められて、免疫抗体が殆ど増加しない可能性がある。
なお、衰弱した子牛は強制投与した初乳が羊水と混合して不完全な凝固状態で「四胃」内に長時間停滞するという。停滞で膨満化した四胃が横隔膜を圧迫して死亡する恐れがある。
このような衰弱子牛には「獣医師の指示で呼吸困難を改善して生後6時間以内に初乳をあたえるべきである」と酪大の小岩教授は述べている。
新鮮な空気を子牛に吸わせるためと体脂肪代謝刺激のためにカウハッチごと子牛を冬の北海道でも寒風すさぶ外気に晒す方がベターであるとされていたが、1~2頭飼い時代の雌牛誕生時のように子牛に毛布を着せて体力を消耗させないように気配りしていた。
さらに、現在の集団哺乳施設では赤外線電球で本格的に暖房をしているが、その方が哺育成績も良いようだ。
牛も改良が進んで豚並に未熟状態で生まれて加温を必要とする時代を迎えているようだ。
哺乳方法もバケツから、がつがつとがぶ飲みさせて口の周りや顎を乳で汚したまま放置されて、かぶれて脱毛する牛がいたが、今はボトルに乳首を付け、母乳を自然に飲んでいた位置で、顎と下を巧みに使って筋力をつけながら唾液の分泌をも促進するなど、生理的にも合理的なグッズを使用するようになった。
しかし、管理する人は早く哺乳時間から開放されたいがために、乳首の穴を大きくしてがぶ飲みと変わらぬ勢いで飲ませて早々にボトルを回収して洗浄する人がいる。人も牛乳を飲むときは牛乳を噛んで飲めといわれたもので、牛にもゆっくり時間をかけて飲ませたいものだ。
哺乳回数も管理の省力化が優先した時代は1日1回哺乳が実行されていた。人の子同様に細かな気遣いを最大限に要求される哺乳さえ搾乳回数に連動した人の御都合に支配されて来た。
人の好都合は家畜にとっては不都合なことが多いと自覚して管理しなければ酪農は儲からないと嘆くばかりだ。
搾乳ロボットが登場したように、最近は精巧な哺乳ロボットが好評を博している。特に、母親任せの自然哺乳が定着している和牛農家は人工哺乳の経験が殆ど無いだけに機械任せのマニュアル通り行うのでかえって成績が良い。
子牛は模擬母牛感覚で少量ずつ1日がかりで飲みたい時に自由に飲める。群飼いのメリットとともに神経質の子牛は人へのストレスが少なくて発育も良い。
ここで哺乳子牛のカウコンフォートは大丈夫だろうか。近年F1生産の高まりとメガファームの大量買付けにより北海道からの導入牛が高値傾向にある。そのため、自家育成が見直されてきたが、相変わらず犬ころのようにロープで牛舎の隅や通路に繋がれた哀れな子牛を目にすることがある。
これはストレスの塊で、下痢ばかりかあらゆる病気の感染試験実施中かと心配させられる。乾燥した清潔な哺育柵やハッチなど将来構想を立てて家族間の労働配分を考慮し、老練な熟年者による気心が知れた自家育成牛による後継牛確保を実現されたい。
本連載は2003年5月1日~2010年4月1日までに終了したものを著者・中野光志氏(元鯉淵学園教授)の許可を得て掲載するものです。