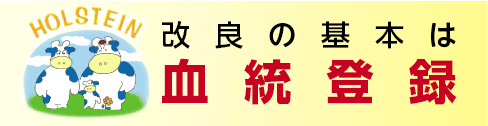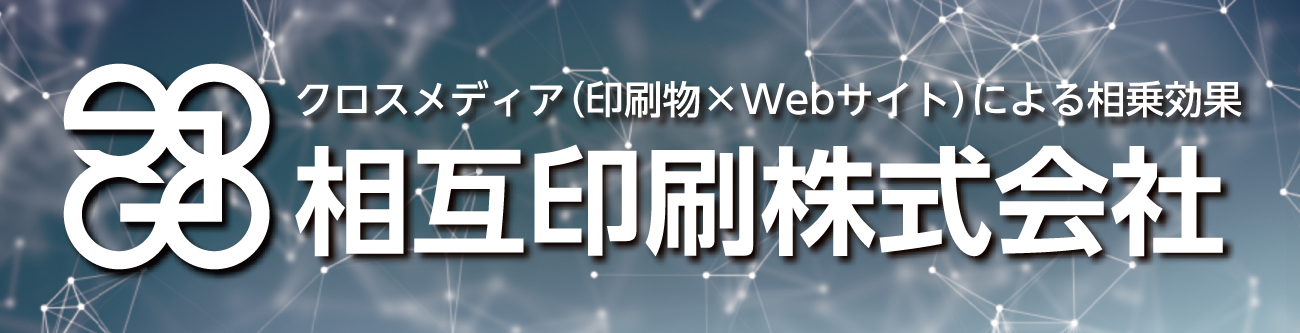後継者、酪農女性に贈る牛飼い哲学と基礎技術
連載21
厄介な耐性菌 抗生物質投与が仇となる 脱薬物依存で動物からの感染防ぐ
新年明けましておめでとうございます。
本紙に「後継者、酪農女性に贈る牛飼い哲学と基礎知識」を連載して2度目の正月を迎え、今回で21回目になった。これまでの連載では、酪農現場の日常的行為の中から次のような話題を提供してきた。
①バルクタンクのスイッチ点燈。これについてはメーカーも賛同してくれた②搾乳中の大腸菌汚染問題は目に見えない大腸菌を培養してピンクコロニーとして確認、この大腸菌が環境性えそ性乳房炎となって死を招く③原乳を電子レンジで殺菌し、継代培養した自家製ヨーグルトを愛飲して「細菌」の存在を自覚④搾乳時の衛生管理の基本は乳頭とティートカップの消毒と乾燥⑤牛の生理・都合にあった時間搾乳の励行⑥牛の健康を反映する体細胞、バルク乳体細胞は15万、牛の7割が10万以下⑦体細胞はほとんどが生存細胞で脱落細胞ではなかった⑧黄色ブドウ球菌は体細胞体内で生存し撲滅困難⑨乳房炎廃牛は年間2万頭⑩脱抗生物質療法・自然治癒は3割強⑪換気扇風向調整で防暑・冬期舎内乾燥―などが主な内容であるが、役に立っただろうか?
さて、本題に入るとしよう。「飛び火患者、3割にMRSA抗生物質の使い方見直しを」。
これは04年10月の新聞記事である。
乳幼児に多い皮膚が膿んだり水泡ができたりするこの「飛び火」患者の3割が抗生物質が効きにくいMRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)を持っている実態を広島大学の細菌学教室が明らかにした。
このMRSAは病院内の院内感染を引き起こすタイプとは異なり、病院外でできた新しいタイプが広がっている。この黄色ブドウ球菌の耐性度は段々強くなっていくので「抗生物質の使い方を見直す必要がある」としている。「患部を消毒したり流水で洗ったりするだけでもかなり効果的である」と、まさに乳房炎原因菌と同類である。
治療や予防原則は、毎日入浴し、石鹸の使いすぎや薬漬け禁止というから人畜共通の原点といえる。
「0-157、複数に薬剤耐性治療指針の抗生物質も効かぬ例」。これは97年7月の第一面トップ新聞記事である。
抗生物質により抵抗力(耐性)を身に付け、投与しても効果がないタイプの病原性大腸菌、0―157、0-26が複数出現していることを愛知県衛生研が明らかにした。
その内容は「5種類の抗生物質(アンピシリン、テラマイ、ストマイ、カナマイ、クロマイ)に耐性を持つ菌が見つかったほか、3割が何らかの抗生物質耐性菌で、1割は厚生省の治療マニュアルの投与例に挙げたカナマイとホスホマイシンにも耐性を持っていた」というもの。
また、「家畜に使用されている大量の抗生物質によって、家畜の体内で菌が耐性を獲得し、ヒトに感染した可能性もある」としている。
酪農家の皆様にはここに列記された抗生物質はあまりにも身近すぎるし、すでに古典的な存在ではなかろうか。
現時点では第3世代(携帯電話の宣伝文句?)の最新抗菌剤を頻用し、すでにこの耐性菌の出現で相変わらず治療効果を低下させている。
さらに、04年10月とつい最近のことであるが、「水俣病関西訴訟判決文」要旨のすぐ上の新聞記事に「台湾産ウナギ、抗生剤を検出厚労省、検査命令」という記事が載っていた。養殖ウナギから含有が認められていない合成抗菌エンロフロキサシンが検出されたという報道だ。
このウナギは全量廃棄か積み戻される。ちなみに、養殖魚の8割以上にクロマイ、テラマイ、サルファ剤、ストマイの4剤耐性が生じているが、ここで注目すべきは、魚類には使用されていなかったストマイ耐性が生じたことである。
ヒトと動物を区別した薬物を使用して、動物からの耐性菌をヒトに伝播させない考え方もこのストマイの例のように使用しなくても、多剤耐性が複数に及んで発生する。薬物依存そのものを改めるしかない現象である。
1969年の英国のスワンレポートには、ヒトの健康を守るためには、いかにして動物からの伝播を防止するかについて報告している。畜産物の薬剤残留によるアレルギー発生、現在は牛乳、卵、果てはそばまでアレルギー源として食品に明記することになっている。
さらに、ヒトへの耐性菌の伝播により抗生物質療法が阻害されると警鐘を鳴らしていたが、MRSAよりさらに難物のVRE(バンコマイシン耐性腸球菌)が鶏肉などから各国に伝播されているとある。
鶏は、集団飼育での疾病予防と成長促進に多量の抗生剤が飼料に添加され、これに伴って治療にも投与されている。これがヒトへの伝播・公衆衛生面からも危惧され、両者の両立も考慮せねばならない。
0-157などは、牛からヒトへ感染するものであると短絡的に牛が悪者扱いされるが、最近の報告では人畜共通の0-157は1割程度だったという。
ヒトからヒトへの伝播による0-157感染症がいまだ後を絶たず、ごく当たり前となっているトイレ後の手洗いで蛇口から感染することもあるし、ドアの取っ手も然りである。
また、肉を切った後のまな板から野菜へ感染することもある。調理は〝75度C、1分でゼロ(0←1←5←7)〟の原則を守れば牛や畜産農家に罪を着せることが少なくなるはずだ。
1998年にEUでスタートした「予防の原則」リスクマネージメントの方法として、科学的に不明確な状況下で重大であるかもしれないリスクに対する必要性を考えて、科学的究明結果を待たずに政治的に使用禁止が決定できるという。
人命尊重は貫かねばならない。では、抗生物質のみならず、肥育ホルモンや泌乳ホルモンに依存しているアメリカ産牛肉は大丈夫だろうか?
本連載は2003年5月1日~2010年4月1日までに終了したものを著者・中野光志氏(元鯉淵学園教授)の許可を得て掲載するものです。